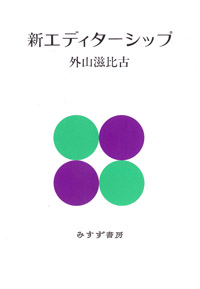トピックス
『新エディターシップ』
外山滋比古 [5月20日刊]
人間はすべて生まれながらのエディターである。本書は、人間がつね日頃何気なく行なっている知的活動の原理を〈エディターシップ〉と名づけ、そのすぐれて創造的な機能を明らかにしたユニークな〈人間文化論〉である。近代的な分析よりも〈結ぶ=つなぐ〉ことに注目し、統合作用による文化創造の原理を鮮やかに論証した決定版。
初版『エディターシップ』(1975年)の当時から、この本は専門の編集者のためだけに書かれたものではなかった。編集関係者は大いに啓発され版を重ねたけれども、もともと一般の人に向けて構想された本である。技術や作業としての編集とは別に、人間が、日常生活で意識しないで発揮する、創造原理としてのエディターシップがこの本の眼目であった。
改訂は著者年来の懸案であったという。このたび冒頭2章の経験談が削られ新稿に差し換えられた。編集の仕事の具体が語られていた「ある経験」「輝かしき編集」の代わりに書き下ろされたのは、その表題も象徴的な「ミドルマン」と「エディター」の2章である。形而上的な原理の考察で一貫する『新エディターシップ』は、まさに決定版であり、新しい思考へと読者を誘うにちがいない。
- マクルーハン『メディア論――人間の拡張の諸相』栗原・河本訳はこちら
- アイゼンステイン『印刷革命』別宮貞徳監訳はこちら
- シャルチエ『書物から読書へ』水林・泉・露崎訳はこちら
- 宮田昇『翻訳権の戦後史』はこちら
- 宮田昇『新編 戦後翻訳風雲録』はこちら
- 名和小太郎『ディジタル著作権――二重標準の時代へ』はこちら
- 名和小太郎『個人データ保護』はこちら
- 長谷川一『出版と知のメディア論――エディターシップの歴史と再生』はこちら