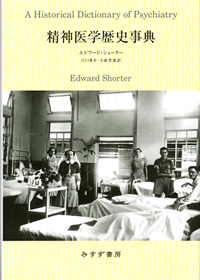
2016.07.29
精神医学の総体を理解するために
エドワード・ショーター『精神医学歴史事典』 江口重幸・大前晋監訳
読み広げる 2016年夏の読書のご案内
2016.07.25
精神科医ヴィクトール・E・フランクルが、ナチス・ドイツの強制収容所に囚われたみずからの体験をつづり、極限状況におかれた人間の尊厳の姿を余すところなく描いた『夜と霧』。世紀をこえ、世代をこえて、読み返され、読みつがれています。
夏休みの青少年読書感想文全国コンクールにも、おもに高等学校の部の自由図書に毎年のように選ばれ、そこから年々すばらしい作品が生みだされています。
『夜と霧』には、池田香代子訳の「新版」(2002年刊)と霜山徳爾訳(初版1956年刊)のふたつの版があります。両方が並行して版を重ねるというたいへん異例の出版です。
新版は、この永遠の名著を21世紀の若い読者にも伝えつづけたいという願いから生まれました。フランクル自身が大幅な改訂をほどこした1977年のドイツ語版にもとづく、真新しい翻訳です。
いっぽう霜山徳爾訳は、終戦から11年めの1956年夏の初版以来、日本でながく読みつがれてきました。当時、ホロコースト(ショアー)やアウシュヴィッツのことはまだよく知られていませんでしたので、ドイツ語版にはない解説や写真資料を日本で独自に加えて編集されました。
新版の刊行をきっかけにして、新旧の翻訳のどちらにもあらためて讃辞が寄せられるという予想しない出来事が起こったのです。どちらの版にも愛読者がいらっしゃいます。切々と思いをこめたお声を、小社もたびたびおきかせいただくことがあります。
…続きを読む »
『夜と霧』のふたつの版はどちらも、現在は電子書籍として配信もしています。
2007年以来、フランクル『夜と霧』から読み広げる読書案内を考えてきました。この夏は、半年ほど前に刊行したドイツの作家グードルン・パウゼヴァングの百冊めにあたる渾身の作『片手の郵便配達人』をご紹介し、また7月初めに訃報の伝えられたエリ・ヴィーゼルを偲びたいと思います。
第二次世界大戦下の1944年8月、主人公ヨハン・ポルトナーは17歳。大きくて体のがっしりした、青い眼に褐色の髪の少年だ。間に合わせの訓練を受けただけでロシア戦線に送り込まれ、2日めに左手を失ったヨハンは、故郷の山あいの村へ戻って、郵便配達人として働いている。
毎日、重い郵便カバンを肩にかけて長い道のりを歩き、夫や息子からの便りを待ちわびる家族に戦地からの手紙を届ける。またあるときは、戦死通知の「黒い手紙」をヨハンは運ぶ。若いヨハンの誠実さ、温かさは、人びとの心を開かせる。時代の狂気に翻弄される村の人びと。みながヨハンに不安や悲しみをあずける。恋人イルメラとの出会い、つかのまの幸福。やがてドイツ降伏、ささやかな平和がおとずれる。ロシア兵が村にやってくる。そして急展開、衝撃的な結末――
1945年5月までの10カ月間の物語です。
「戦争とは非情なまでに人間を痛めつけ、破壊していくものです」と、作者パウゼヴァングは巻末に収められた「日本の皆さんへ」できっぱり述べています。
(「日本の皆さんへ」『片手の郵便配達人』巻末231-233ページ)
パウゼヴァングは1928年、当時ドイツ領だったボヘミア東部(現チェコ)生まれ。ヒトラー自殺の報に泣き、17歳で敗戦を経験したかつての軍国少女が、「証言者はまもなくいなくなる」と、戦後生まれの世代、若い世代、21世紀生まれの世代に向けて書きつづけてきました。
70年をかけて熟成されたすべてを投げ入れ、このパウゼヴァング百冊めにあたる長篇小説『片手の郵便配達人』は書かれています。既刊の短篇集『そこに僕らは居合わせた』と併せ読んでいただけたら、きっとうなずかれるに違いありません。
証言者はまもなくいなくなる。悲しいことですが、人のいのちには限りがあります。エリ・ヴィーゼルの訃報が伝えられました。パウゼヴァングと同年1928年生まれのユダヤ人作家。1944年アウシュヴィッツの強制収容所に入れられ、翌年ブーヘンヴァルトの強制収容所で解放を迎える。帰郷を拒んでパリのソルボンヌ大学に学び、のち新聞記者となり、渡米。1986年ノーベル平和賞受賞。ボストンに住み、フランス語で文筆活動を続け、去る7月2日、ニューヨーク市マンハッタンの自宅で死去。
けれどもロングセラー『夜』は生きつづけます。ホロコーストの極限状態を崇高に綴る自伝的小説。
この夏、フランクルの著書3点を新装復刊します。
『時代精神の病理学』『識られざる神』『神経症』。いずれも少しむずかしそうな表題にみえるかもしれませんが、フランクルは精神医学者として、人間が存在することの意味への意志を重視し、心理療法に活かすという、実存分析やロゴテラピーとよばれる独自の理論を展開しました。これらの3冊は、専門家向けというよりは、たえずみずからの体験に立ちかえりながら、平易な表現で、精神医学や心理療法をこえて、人間存在の根源についての考え方を明らかにする本です。
朝日新聞のコラム、鷲田清一「折々のことば」で7月21日に、成田康子「高校図書館から」の一節が引かれたのをお読みの方もおいででしょうか。
〈「これってこうだよ」ではなく「それってどうなの?」って訊(き)いてくれるから〉
この一文が、ある高校生のことばとしてコラムにとりあげられました。月刊『みすず』7月号に載った成田康子「高校図書館から――『わが闘争』、そして」で描かれるのは、ヒトラー『わが闘争』をめぐる、ひとりの女子生徒と図書館司書の著者とのエピソードです。
そのはじまり近く、
「短い休み時間にひんぱんに来る生徒はめずらしい。私と話をするわけでもない。何かを調べに来ているようす。
あるとき、1冊の文庫本を手にして近づいてきた。
「これって、図書館に置いていていいんですか?」
「ああ、この本ね」
『わが闘争』(アドルフ・ヒトラー)である。
「本国では発禁だと思いますが……」と、ドイツと日本のハーフの彼女の声にとまどいが感じられた」(成田康子「高校図書館から」、『みすず』2016年7月号6ページ)
成田康子『高校図書館――生徒がつくる、司書がはぐくむ』(2013年刊)には、いくつもの試みの実践がいきいきと記録されています。
月刊『みすず』7月号からもう1篇、ブレイディみかこ「子どもたちの階級闘争」11「コスプレと戦争と平和」をご紹介。「子どもたちの階級闘争」は、現在イギリスで保育士として働く著者の「底辺託児所」レポートの連載です。
今回、主役は保育所の「ドレスアップ」のコーナー(英国の保育施設には必ずあって、そこに並べてかけてあるさまざまのコスチュームを着て自由に遊べるのだそうです)で、たまたま寄付されてそのまま置かれていた軍服を、姉のボーイフレンドと同じ服だから誇りをもって着込んだ小さな女の子ケリーです。が、その本題に入る前に、著者の9歳の息子がかよう小学校で、授業の一環として、戦時中の疎開児童の恰好をして学校に行くという話がふれられています。
著者は昼間、学校のある時間帯に、息子の筆跡で母と父にあてられた手紙をうけとるのですが、「今朝、あなたたちにさよならを言ったとき、僕の胸は哀しみに潰れてしまいそうでした」……? 両親ふたりで読み返し、ようやく「第二次世界大戦」の学習で疎開児童の恰好をして登校した日があったこと、その日に授業で疎開児童になったつもりで手紙を書きなさいと言われて書いたのだろうということに思い当たるのです。
「英国の小学校はこういうことをよくやる。昨年は、息子たちの学年全員がヴィクトリア朝時代の子どもの労働者(男子は煙突掃除の少年、女子はメイド)の恰好をして登校し、学校の近くのヴィクトリア朝建築の建物の中で当時の貧困層の子どもの生活を疑似体験するという授業があった。その授業の後で、うちの息子はやたらと「ヒューマン・ライツ」という言葉を口にするようになった」(「子どもたちの階級闘争」11「コスプレと戦争と平和」、『みすず』2016年7月号57ページ)
考えさせられます。戦争体験のないわたしたちが、どのようにしてリアリティをともなって戦争というものに想像力をとどかせることができるのか、どこからとりつけばよいのか、2007年以来このコーナーでずっと考えてきたことですが、まだまだ柔軟に、想像をはたらかせる余地はいっぱいひらけてきそうです。
カバー](/_wp/wp-content/uploads/2016/07/03970.jpg)
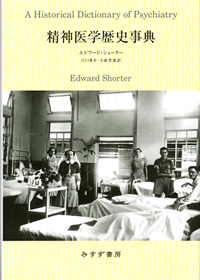
2016.07.29
エドワード・ショーター『精神医学歴史事典』 江口重幸・大前晋監訳

2016.07.15
今福龍太『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』