
2015.07.01
『失われてゆく、我々の内なる細菌』
マーティン・J・ブレイザー 山本太郎訳
2015.07.01
長田弘さんの『最後の詩集』をなんとか出版してホッとすると同時に、ご本人から感想を聞けることはないのだな、と寂しい思いにとらわれています。これまで詩集が出来たときには、かならず労いの言葉に添えて当方をうれしがらせるような一言を下さいました。こんどの本についてある方から、「アレッツォのフレスコ画の木の表紙、誰よりも長田さんがお喜びではないでしょうか」と言っていただき、せめても救われる思いです。
著者の没後に本を作ることは、長年出版社に勤めている大抵の者が経験することでしょう。しかし、私にとってこんどと同じように大きな思い出は、須賀敦子さんとの仕事でした。1997年11月に刊行した、イタロ・カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』(その後、河出文庫)の翻訳の校正を、須賀さんは入院中の病室で済ませました。結果としてこれが生前最後の本になります。翌年3月20日に亡くなってから幾つかの出版社が、連載をまとめた本やエッセイ集などを矢継ぎ早に出しましたが、私に残された約束は、数年間にわたって少しずつ渡されて溜めてきた、ウンベルト・サバの詩稿の刊行でした。サバの詩集『最後のこと』や『地中海』からは、もっと訳したい詩があったと思いますが、須賀さんにはもう時間が残されていませんでした。
校正刷を読んで赤字を入れてくれる著者はすでにありません。一人で何度も読んでは、不在の人に向かって自問自答のようなことを繰り返しつつ、没後の数ヶ月を過ごしました。『ウンベルト・サバ詩集』が出たのは9月10日です。須賀さんに見せたらきっと、布表紙の芥子色について何か食べ物の比喩で評したり、背中に紺で箔押しされた書名を撫でながら軽い冗談を言ったりしてくれたことでしょう。そんなふうに本の話を須賀さんとするのが、こちらにとっては無上の喜びでした。
いっぽう、長田弘『最後の詩集』の場合はやや成り立ちが違います。『長田弘全詩集』の準備を昨年の秋から共に進めながら、全詩集のつぎに出るのは「最後の詩集」になると思いますという、長田さんの意志(覚悟という言葉は似合いません)を受けとめていました。そして、亡くなった後に託されたのは、推敲と構成を終えた一群の詩稿と、初出に関する覚書、「本書を以て決定稿とした」という結語でした。
遺稿を本にするなかで、須賀さんと長田さんとの仕事が、お二人の違いをこえてわたしに重なるのは、きっと二人とも無類の本好きだったからだと思います。須賀さんは「本に読まれ」るような少女からミラノの書店員になり、長田さんは本を糧にする少年から編集者になりました。
詩というのは、音楽のように、何度でも読めます。読むたびに同じ感情にさそわれながら、少しべつのことを考えさせられます。これは親しい人と話しているのに近いのではないでしょうか。「その静かな界隈には詩人がひとり、/死んだ者たちの生きた碑銘を/誠実で、あかるい、作品に織っている。」(ウンベルト・サバ「自伝」より。須賀敦子訳)「花々と樹々のあいだの細い小道を、/わたしは、本を読むように歩いてゆく。」(長田弘「アッティカの少女の墓」より)
本を読み、本を作るだけでなく、本について語り合う時間をすぐれた方と持てたこと。そして、お二人の残した「詩集」の製作を担当できたことに感謝します。
(編集部・尾方邦雄)

2015.07.01
マーティン・J・ブレイザー 山本太郎訳
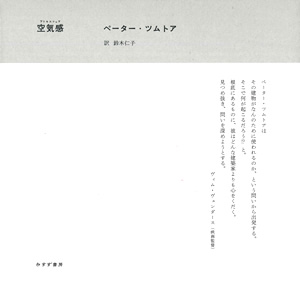
2015.06.25
鈴木仁子訳