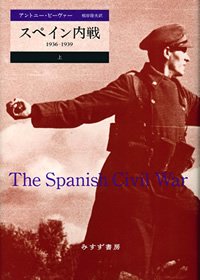トピックス
A・ビーヴァー『スペイン内戦』
1936‐1939 根岸隆夫訳 [全2巻]
ゲルニカの町が空襲されたのは1937年4月26日。市の立つ日で、たくさんの農民が近郊から牛や羊を連れて集まっていたという。爆撃したのは、フランコ将軍指揮下の国民戦線軍(反乱軍)に加担したドイツ空軍、コンドル兵団。率いるフォン・リヒトホーフェン大佐は「空襲テロの大実験」を兼ねていた。迎え撃つはずの共和国政府軍(人民戦線軍)は手の打ちようがなかった。
ピカソはその6日後に、壁画「ゲルニカ」の制作にとりかかる。
ゲルニカはスペイン北部、バスク地方の最大の都市ビルバオの東20キロに位置し、ビスケー湾から南に10キロほど下った古都だ。
ゲルニカ崩壊の知らせは、ビルバオにいた外国の新聞特派員たちによってすぐ本国に打電された。28日にはジョージ・スティーアの記事が『ザ・タイムズ』(ロンドン)と『ニューヨーク・タイムズ』に掲載され、これは国際的に途方もない反響を呼ぶ。「ゲルニカ」のイメージはここで決定的になった。ピカソの壁画は悲劇を象徴する存在として有名になる。
内戦は、ファシズム対反ファシズムの戦いとして、人々の脳裏に焼きつき、両陣営の宣伝戦も激しさを増した。世界の芸術家と知識人たちの関心を、前例のない規模で集め、彼らの去就を決めさせることにもなる。しかもその圧倒的多数が、「反ファシズム」を掲げて共和国側についたのは自然のなりゆきだっただろう。曖昧な態度をゆるさない空気が支配していたという。
状況は当時の日本でも共有されていたようだ。ヒュー・トマス『スペイン市民戦争』(都築忠七訳、みすず書房、1963)は資料の制約のなかで描かれた記念碑的な通史で、当時、この本を通らずにスペイン内戦を語るなと絶賛されたが、出版社による宣伝文は熱かった。
「スペイン市民戦争は、1930年代の世界が、かたずをのんで見守った、人民戦線とファシズムの巨大な激突のはしりである。流血むなしく人民戦線は没落し、それはついに第二次世界大戦の悲劇の序奏となった」
ビーヴァーの『スペイン内戦』は、膨大な新資料の裏づけと、バランスのとれた叙述で、すべての「神話」を一度解体し、新たにこの20世紀を象徴する戦いを理解しようとする、画期的な試みの成果だ。たんなる右翼と左翼の戦いでも、ファシズムと反ファシズムの戦いでもなく、いくつもの対立の軸が複雑に絡み合っていたことが、説得的に描かれる。
- V・ザスラフスキー『カチンの森』(根岸隆夫訳)はこちら
- R・ジェラテリー『ヒトラーを支持したドイツ国民』(根岸隆夫訳)はこちら
- リード/フィッシャー『ヒトラーとスターリン』上(根岸隆夫訳)はこちら
- リード/フィッシャー『ヒトラーとスターリン』下(根岸隆夫訳)はこちら
- W・G・クリヴィツキー『スターリン時代』第2版(根岸隆夫訳)はこちら
- J・ジョル『ヨーロッパ100年史』 1 (池田清訳)はこちら
- J・ジョル『ヨーロッパ100年史』 2 (池田清訳)はこちら
- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』上(森本醇訳)はこちら
- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』下(浅沼澄訳)はこちら
- トニー・ジャット『荒廃する世界のなかで』(森本醇訳)はこちら
- H・アーレント『暴力について』(山田正行訳)はこちら
- 『イーデン回顧録』全4巻セット(湯浅・町野・南井訳)はこちら
- 『レーモン・アロン回想録』 1 (三保元訳)はこちら
- 『レーモン・アロン回想録』 2 (三保元訳)はこちら