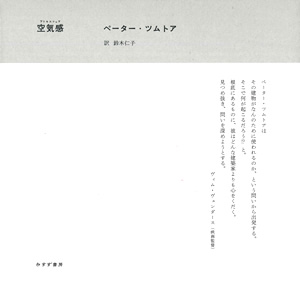
2015.06.25
ペーター・ツムトア『空気感(アトモスフェア)』
鈴木仁子訳
聞き手 ティモシー・スナイダー 河野真太郎訳
2015.06.25
トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』が英米で刊行されたのが、ちょうど10年前。『タイムズ文芸付録』恒例の「今年の収穫」で、歴史学者ティモシー・ガートン・アッシュが強く推しているのをみて興味を抱いた。ジャットは、ロンドンに育ち、ケンブリッジとパリで学び、オクスフォードで教えた後でアメリカに渡って、ニューヨーク大学に研究所を創設してヨーロッパ研究をしている学者評論家らしい。知的エリートだという以外の想像はしなかった。
ところが、取り寄せた原書を拾い読みすると、映画やポピュラー音楽にたいするセンスがやけにいい。「マリア・ブラウンの結婚」や「第三の男」を引き合いに、戦後のベルリン、ウィーンの状況をありありと浮かび上がらせる。ビートルズの出現を、直前のスキッフルと比較しつつイギリスの若者社会の変化をくっきり捉える。1948年生まれの(日本なら「団塊世代」どまんなかの)トニー・ジャットに、すっかり感心してしまった。いったいこの男、何者なんだろう?
それから三年、『ヨーロッパ戦後史』の翻訳上下巻を出した頃に、残念ながらジャットは不治の難病ALSにかかり、2010年8月6日に亡くなった。格差社会にたいする警世の書『荒廃する世界のなかで』も、病床から『ニューヨーク・レヴュー・オヴ・ブックス』に連載した自伝エッセイが『記憶の山荘』として一冊にまとまったのも、没後の出版である。元気なときに構想していた大著(たとえば『鉄道の社会史』)はついに書かれずに終わった。
そのかわり読者は、ジャット自身の充実した生涯に関してだんだん知ることになったのである。自分は、一方で「イギリス下層中産階級そのものといった1950年代の子供」であり、その一方で「中欧東部出身のユダヤ人移民の経験に特権的に集約された20世紀中葉の歴史の表れ」だと、本書『20世紀を考える』の冒頭でジャットは言っている。
こういう複眼的な視点こそ、ジャットの学問の魅力の根源といえよう。少年時代の思い出(楽しいことも悲しいことも)を、都市交通の変化や戦後平等教育の理念に重ねる。キブツ運動にオルグされて夏休みをイスラエルで流した汗の記憶(懐かしさも反省も)を、パレスチナ問題を論ずる起点にする。パリの高等師範学校の雰囲気を体験した実感を、フランスのエリート教育や左翼知識人の本質論につなげる。
いっぽう聞き手のティモシー・スナイダーは1969年生まれ、気鋭の東欧史学者である。学生時代にジャットの論文を読み、面識を得てオクスフォードに留学した。でも二人はけっして「師弟」として語り合うのではない。本書には「二人の精神が対話を通じて果断に格闘した際の自発性、予測不可能性、そしてときには遊びが反映されている」と、スナイダーはまえがきで書いている。
ホロコーストとシオニズム、ファシズムと共産主義、20世紀を大きく動かしたテーマと観念を、この対話は生きもののように扱おうとする。さらに時代のイデオロギーを支えた知識人たちの言論について厳しい批評をくわえる。なにしろ「つぎの世代でわたしたちが直面する選択肢は、資本主義か共産主義か、または歴史の終わりか歴史の回帰か、ではなく、集団的な目的にもとづく社会的な結束か、それとも不安の政治による社会の腐食か、というものになります」とさらっと言ってのける直感力がすごい。そして本書の全体にドライブ感をもたらしているのが、恋愛についても率直に語られるジャットの人生だ。
これからはもう、ジャットの新著は出ないと思う。それでも満足しよう。日増しに動かなくなる身体をもてあましながら、強靭な精神をもつ歴史家が記憶だけをたよりに繰り出す議論を受け止め、理解し、反論し、本書にまとめあげてくれたスナイダーに感謝しよう。第一次世界大戦が始まった年のように、前世紀が終わりを告げつつ、その記憶も失われつつある時代に、ジャット最後の本『20世紀を考える』が与えられたことを、編集担当としてより、むしろ読者として喜びたい。
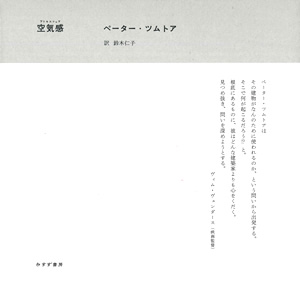
2015.06.25
鈴木仁子訳
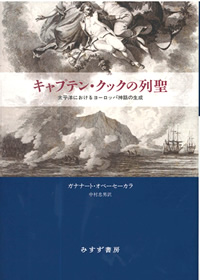
2015.06.11
太平洋におけるヨーロッパ神話の生成 中村忠男訳