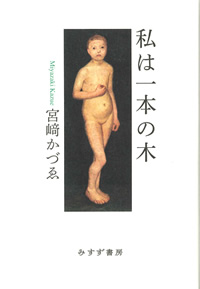
2016.02.10
富山英俊訳
2016.01.28
なんと雄渾な、しかも大胆に圧縮された歴史文学でしょうか。まるでユーコン河3700kmを3日で流れ下るような(すみません、駄洒落です)。
とはいえこれは、滔滔と紡がれる大河ドラマのダイジェストではありません。いたるところに断層があり、急流があり、瀞があり、中洲がある。ただひとりのナレーターによる歴史語りだと、どうしても原因があって結果がある出来事の連鎖になってしまう。そこでウィリアムズは、矛盾や虚構をもおそれず、ナレーターを変え語り口を変え、ときには日記や手紙や文献を、注釈も加えずそのまま提示します。
これが事のありさまだ、ソールの民会よ。これが始めからおれのありさまだった。エイリークは友を愛し、寝床を愛し、食い物を愛し、狩りを愛し、息子を愛する。槍を投げ、女を抱き、船を操り、土地を耕し植えて、家畜を育てる男だ。狐の皮を剥ぎ、歌い、踊り、走り、格闘し、登り、アザラシのように泳ぐ。
ここで語っている「おれ」は、中世北欧のヴァイキング「赤毛のエイリーク」です。エイリークの息子レイヴは、コロンブスより500年も前の1000年ごろ、ヨーロッパからアメリカ大陸に到達しました。ウィリアムズは、赤毛のエイリーク自身に語らせるために、あえてアイスランド・サガの無骨な調子をまねているのですが、ではこの「おれ」は、いったい誰に向かって語っているのでしょうか。16世紀になってやっとイングランドからアメリカに上陸したピューリタンの末裔、つまりウィリアムズも含めた現代のアメリカ人に、です。
それにしてもこのエイリークの語り口は、たとえばこんな一節を思い出させませんか。
「いまここにアルモリックの岸辺に来た。僕の日程は終わった。僕はヨーロッパを去るよ。海の風は僕の肺を燃やす。辺境の地は僕の肌をなめす。泳ぎ、草を噛みくだき、猟をし、とりわけ煙草を吹かすんだ。沸騰する金属のように強い酒を飲もう、――あのなつかしい先祖たちが火のまわりでしたように」(鈴村和成訳)。
アルチュール・ランボー『地獄の季節』の一節です。ランボーが、正統的なフランス人(カトリック)の血統から身を引き離すために、あえてみずからを劣等人種になぞらえるように、ウィリアムズは、正統的なアメリカ人(ピューリタン)とは別の血統のありかを、新世界の歴史のなかに探ります。
獰猛に無慈悲に、ぼくたちはかれらを殺す。だがかれらの魂が、ぼくたちを支配する。ぼくたちという人間。その血統。だがかれらの精神が、主人だ。ぼくたちに入り込み、打倒し、己を押しつける。
ここで言う「ぼくたち」は、ピューリタンの末裔である現代のアメリカ白人。「かれら」とは、カリブ族でありインディオ、つまりアメリカの先住民です。
本書の原題は”In the American Grain”です。”Grain”とは「種子」、または「特質」のこと。アメリカ人の特質はその種子のうちに宿る。種子であるからには潜在的に血統を受け継いでいるわけですが、その種子が芽を出し、十全に育つためには、まず大地に播かれなければならない。
ウィリアムズにとって、われわれ人間もまた大地から生い育つ草です。もちろん比喩ですが、「民草」という言葉もあるくらいだから突飛な比喩ではないでしょう。インディオたち先住民が在来種だとすると、ピューリタンたちは外来種です。かれら外来種は、蘭のように美しい新世界を前に、豊穣な大地の精(魂)を吸収して、在来種と混交し、雑種化し、ともに繁茂して大輪の花を咲かせ、他家受粉し、しなやかな実を結ぶのではなく、むしろ大地の豊かさを怖れ、否認し、己の硬い殻に閉じこもり、勤勉と倹約にのみ励み、馥郁と花開くことなく、いじけた実しか結ばなかった、というのが、ウィリアムズのアメリカ史観です。
本書の序言で、ウィリアムズはこう言います、「ぼくの望みは、すべての源泉から、ひとつのもの、命の不思議な燐光を抽出することだった」。「命の不思議な燐光」――これは、新世界に最初に播かれた種子のうちに孕まれていたはずの、燐光でしょう。ここでまた別の一節が思い浮かびます。「過去の真のイメージは、ちらりとしかあらわれぬ。一回かぎり、さっとひらめくイメージとしてしか過去は捉えられない」(ヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について」野村修訳)。
「さっとひらめくイメージ」としての、「命の不思議な燐光」。一回かぎりの、ちらりとしかあらわれないイメージ(燐光)を捉え、そこにありえたかもしれない別の歴史を指し示すこと。詩人ウィリアムズがアメリカ史の本を書いた動機は、そこにあったように思います。
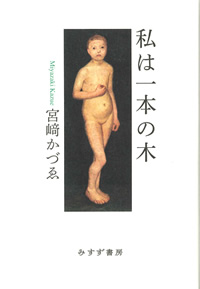
2016.02.10
![アガンベン『身体の使用』上村忠男訳(みすず書房)カバー[「ホモ・サケル」シリーズ最終巻]](/_wp/wp-content/uploads/2016/01/07964.jpg)
2016.01.26
脱構成的可能態の理論のために 上村忠男訳