
2013.09.26
アーレント『反ユダヤ主義』『アイヒマン論争』
ユダヤ論集[全2巻] コーン/フェルドマン編 山田正行・大島かおり・矢野久美子・齋藤純一・佐藤紀子・金慧訳
科学と社会における信頼の獲得 藤垣裕子訳
2013.09.26
社会の数値化をめぐる政治と文化を、科学史家が徹底追求。ひるがえって自然科学における数値化の意味を照射する。
巻末に、科学技術社会論をリードする訳者の明快な「解題」つき。その抜粋をご紹介します。
藤垣裕子
(訳者)
数値にした瞬間に一人歩きしてしまうものは世に多くある。GNP然り、OECDの各種指標然り、研究評価の数値然り、である。たとえば、OECDのPISA(学習到達度調査)の結果が三年に一度公開されるたび、「日本は科学的応用力で先回△位だったのに▽位に落ちた」などの記事が掲載される。しかし、過去三回の調査において問題は同じだったのか、参加国数は同じだったのか、各参加国において生徒の選び方は同じだったのか、などなどを吟味せずして順位という数字だけ比べるのは無意味である。また、福島第一原発事故の直後は、放射線量が△シーベルトという数字がやはり多く報道されたが、それが瞬間のものなのか、時間あたりなのか、年間の被曝線量なのか、といった単位に無頓着で数字だけが騒がれていた時期があった。
巷で流通している数値をそのまま信用するのではなく、一つの数値が定義されるその場面に立ち返って数値を再考することが必要である。何を無視し、何を重要なものとするか、何をノイズとして何をシグナルと見なすか、その判断によって数値の近似の仕方が異なり、一つの数値の算出の仮定が異なり、ひいては数値の値そのものも変わるのである。そのような近似と仮定のプロセスを無視して、算出された数値そのものを客観的で、どこにでも通用するグローバルなものとしてとらえるのは大きな間違いである。
それではなぜ、そのような数値が客観的と見なされて流通してしまうのであろうか。本書は、科学論の専門家として、この問いを史実にもとづいて徹底的に探求した書物である。曰く、ローカルノレッジ(局所的な知識)が通用しなくなるとき、厳密さや標準化が求められ、新しい信頼の技術として「数」が登場する。つまり、経済であれ、知識の流通であれ、グローバル化がすすみ、遠くはなれた地域のひとびととモノや知識の交易をすすめようとするときには、個人由来の知識や地域に依存した知識は使いにくくなる。そういうときに交易や交流の標準化に役立つのが数値なのである。だから、数値とは「没個人化」のための道具なのである。数値は、没個人化に役立ち、個人の技能は最小限にしか要請されなくなる。しかし同時に、数値だけではだめで、それを解釈するための個人の技能やローカルノレッジが逆に必要とされる場面がある。ポーターはこのように、グローバリゼーションによる標準化の動きと、局所共同体における専門的知識やローカル・ノレッジの必要性とのあいだの「信頼」をめぐる闘争を、丁寧に描き出している。数値に興味をもつ一般の方々、社会統計にかかわる方々、そしてそれを読解して政策に役立てようとしている方々など、多くの方に示唆を与えてくれる本である。
本書の展開のなかでもっとも興味深いものの一つは、数値によせる信頼とエキスパート・ジャッジメント(専門家判断つまり個人の技能)によせる信頼の対置である。特に第5章でこれが史実にもとづいて刺激的に展開される。
ふだん、定量化とは、不当な政治的圧力が加わらなければ、厳密性や客観性を追求するために推進されると言われている。しかし、本書は逆の立場をとる。定量化とは、力をもつ部外者が専門性に対して疑いを向けたときに、その適応として生じる。政治的圧力さえなければ客観性が保てるのではなく、政治的圧力があるからこそ、客観性がつくられる。また、アカウンタビリティ(説明責任)によって客観性が弱体化されるのではなく、アカウンタビリティによって客観性がつくられるのである。
(……)
興味深いのは、ここから「客観性の文化研究」とも言える視点がでてくることである。(……)イギリスの文化状況は、紳士であることに敬意と信頼が払われ、「単なる技術専門家」「ただの計算」よりも紳士の判断の方が重要だったのである。(……)フランスではエコール・ポリテクニーク出身者であることに敬意と信頼が払われ、「ただの計算」よりもエリートの判断および自由裁量の方が重要だったのである。(……)それに対してアメリカでは、判断の基準が常に公衆の目に晒され、オープンにされる必要があった。(……)アメリカの20世紀前半の文化状況は、量的な計算手続きの方が信頼されたのであり、エキスパート・ジャッジメントは信頼されなかった。
(……)
「科学的」とは、どの国にも成立するグローバルなことだと考えられている。しかし、本書にあるように、エキスパート・ジャッジメントや自由裁量への疑いの視線の強さが文化によって異なり、オープンネスや明示的手続きへの要求の度合いが異なり、そのことによって、個人の恣意性や距離を越える技術としての定量的手続きの発達の仕方が異なる。このように、専門家の信頼の形成のされ方、自然科学への信頼の形成のされ方、社会科学への信頼の形成のされ方が文化によって異なる様相を見せる場合、知識の妥当性の根拠としての「科学的」で必要とされること(例、没個人的客観性)が文化によって異なる発達の仕方を見せ、それによって、各国の各分野形成が影響を受けることは十分考えられることである。これらは、科学と社会の関係の構築を研究対象とする科学技術社会論にとってたいへん示唆的である。
(……)
本書は科学者の社会責任論への示唆も与える。それを考察してみよう。第8章に「主観性が責任を創るのである」という記述がある。逆にいえば、没個人的な規則にのっとった判断をするかぎり、責任は生じない。手続に従ってさえいれば、責任は免れる。危機管理において規則が強調されるのはそのせいであろう。では、没個人的な規則の方が責任を担うようになった場合、「エリートの矜恃」と呼ばれるものはどうなるのだろう。
(……)
専門家同士も衝突することがしばしば見られたアメリカの政治文化は、科学的知識を幅のあるものととらえ、社会への助言も幅のある形で示し、あとは国民に選択してもらう形を整備してきた。イギリスでは、専門家同士でも意見が衝突することが、高校の理科の教科書にも明記されている。それはイギリスの科学者集団がBSE渦以後、外からの圧力に晒されてきた結果、科学者集団と社会との関係が変容してきた結果である。もし日本の科学者集団が戦後すぐの科学者共同体の理想をそのままかかげ、民主主義の体現としての科学者集団が一つの合意された「助言」をするというモデルに固執するとすると、それは社会との齟齬を生むことになるだろう。行動指針となる一つの統一見解を出すのが責任なのか、それとも幅のある助言をして、あとは国民に選択してもらうのが責任か。それは社会との関係の成熟の度合いによって変容していくものだろう。本書はこのように、客観性の文化研究だけでなく、科学者集団と社会との関係の文化研究に広く道を拓くのである。
copyright Fujigaki Yuko 2013
(訳者のご同意を得て抜粋掲載しています。もとは全5節で構成された長文の解題です。ぜひ全文をお読み下さい)


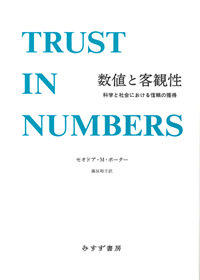

2013.09.26
ユダヤ論集[全2巻] コーン/フェルドマン編 山田正行・大島かおり・矢野久美子・齋藤純一・佐藤紀子・金慧訳

2013.09.12