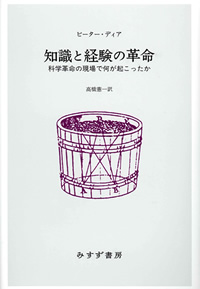トピックス
ディア『知識と経験の革命』
科学革命の現場で何が起こったか 高橋憲一訳
17世紀の「科学革命」と言われてきたものの核心とは。訳者からこのウェブサイトのために、ひとことをお寄せいただきました。
科学革命について物語ること
高橋憲一
このところ科学史業界では「科学革命論」が盛況を見せている。かつてのように、迷信から科学へといった啓蒙主義史観が唱えられることはなくなったが、その科学の成立をめぐっては議論が喧しい。はたして科学革命と称することのできる単一の歴史的出来事があったのかどうか、その歴史的内実はどのようなものとして捉えることができるのか、そもそも科学の成立として捉えてよいものか、自然哲学とキリスト教の関係が変貌していくプロセスではなかったか、等々。欧米での議論を紹介する形で、関連する著作が日本語に訳されている。主なものではSteven Shapin, THE SCIENTIFIC REVOLUTION (1996) [『「科学革命」とは何だったのか:新しい歴史観の試み』、川田勝訳、白水社、1998]、John Henry, THE SCIENTIFIC REVOLUTION AND THE ORIGINS OF MODERN SCIENCE (2002) [『17世紀科学革命』、東慎一郎訳、岩波書店、2005]。未邦訳のものでは例えば、Lisa Jardine, INGENIOUS PURSUITS: Building the Scientific Revolution (1999)、Wilbur Applebaum (ed.), ENCYCLOPEDIA OF THE SCIENTIFIC REVOLUTION: From Copernicus to Newton (2000)、Applebaum, THE SCIENTIFIC REVOLUTION AND THE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE (2005)、Margaret J. Osler, RECONFIGURING THE WORLD: Nature, God, and Human Understanding from the Middle Ages to Early Modern Europe (2010) がある。ピーター・ディア氏の著作(初版2001年、第2版2009年)もこの流れに乗っている。
本書の原題はREVOLUTIONIZING THE SCIENCES: European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700である。「科学革命the Scientific Revolution」という通常の表現をタイトルに使わなかったところに、著者のセンスの良さがうかがえる、といったら訳者の贔屓がすぎるだろうか。直訳すれば、とりあえずは「科学に革命を起こす」となろうか。でもまだ意を尽くしたとは言い難い。最大の問題あるいは難点は、Sciencesの翻訳である。科学、学問、知識のいずれがよいだろうか? 英語の源流をたどれば、ラテン語のscientiaにいくだろうし、ギリシャ語まで遡ればepisteme* に行き着くだろう。そうなれば先の三つの言葉を一つに集約した日本語があればベストということになるのだが、どうもそうはいかないようである。そこで訳者と編集者の共同作業の結果が、標記の邦訳書名となったわけである。17世紀の「科学革命」と言われてきたものの核心は、知るということの内実・方法・目的および経験の再編における大きな変革にあった。このように主張する著者の意図に沿っているのではないかと訳者たちは秘かに自負しているのだが、果たしてどうだろうか。
我が国の科学思想史研究の先達であった下村寅太郎氏はかつて、科学史は「科学の歴史」ではなく「科学への歴史」であると喝破された(「科学史の哲学」、『下村寅太郎著作集』第1巻** に所収)。現代科学の祖形を遡って探求するのではなく、現代の姿へと科学が自己塑型・変貌してきた様を跡づける営為が科学史である、と。それは、現在の科学およびその活動を相対化する視座の獲得と言い替えることができよう。Fukushimaの大(人災)事故から1年が経った。科学信仰イデオロギーからの脱却がますます必要とされているように思われる現在、本訳書が多くの日本人に、特に若い方々に読んでいただくことを願っている。
copyright Takahashi Kenichi 2012
- * epistemeの2つめと3つめのeにはアクセント記号がつきます。ブラウザでは正しく表示されませんがご諒解下さい
- ** 『下村寅太郎著作集』第1巻『数理哲学・科学史の哲学』は品切重版未定ですが、シリーズ《始まりの本》の一冊として、下村寅太郎『科学史の哲学』の刊行を予定しています
- C・ギリスピー『客観性の刃――科学思想の歴史』[新版]島尾永康訳はこちら
- C・ギリスピー『科学というプロフェッションの出現』島尾永康訳はこちら
- T・S・クーン『科学革命の構造』中山茂訳はこちら
- T・S・クーン『科学革命における本質的緊張』安孫子・佐野訳はこちら
- T・S・クーン『構造以来の道――哲学論集1970-1993』佐々木力訳はこちら
- E・セグレ『古典物理学を創った人々』久保・矢崎訳はこちら
- A・ファントリ『ガリレオ』大谷啓治監修・須藤和夫訳はこちら
- B・J・T・ドッブズ『錬金術師ニュートン』大谷隆昶訳はこちら
- A・コイレ『プラトン』川田殖訳はこちら
- R・G・コリングウッド『自然の観念』平林・大沼訳はこちら
- E・カッシーラー『認識問題』 1 須田・宮武・村岡訳はこちら
- E・カッシーラー『認識問題』 2-1 須田・宮武・村岡訳はこちら
- E・カッシーラー『認識問題』 2-2 須田・宮武・村岡訳はこちら
- E・カッシーラー『認識問題』 4 山本・村岡訳はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 1 はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 2 はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 3 はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 1 はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 2 はこちら