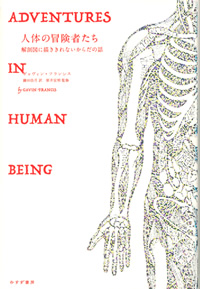
2018.07.23
『人体の冒険者たち』第1章ウェブ転載。ギャヴィン・フランシスの臨床医学的博物誌!
G・フランシス『人体の冒険者たち――解剖図に描ききれないからだの話』 鎌田彷月訳 原井宏明監修
ロラン・バルト『声のきめ――インタビュー集 1962-1980』松島征・大野多加志訳 [17日刊]
2018.07.13
まず書名のことから説明したい。「声のきめ」(Le grain de la voix)という書名は、バルトの没後一年目にスイユ社がこのインタビュー集を刊行したとき編集者によって付けられた。書名となった言葉は、もともとバルトが音楽雑誌に寄せた声楽論のタイトルである(評論集『第三の意味』に収録)。そこでバルトは「grain」という語を「歌う声における、書く手における、演奏する肢体における身体」のことだと独自に規定して、「私は、歌う、あるいは、演奏する男女の身体と私との関係に耳を傾けようと決意している」とまで書いている。粒立ちとか、感触とか、さまざまに訳すことはできるだろうが、これまで「声のきめ」あるいは「声の肌理」として言及されてきた本であるし、「肌」という文字にどこか違和を感じるので、「声のきめ」とした。
無署名の短いまえがき(書いたのは編集者フランソワ・ヴァールか)に「あのエクリチュールの針状体をあの声のきめ(粒状体)に結びつけつつ対抗させているもの」という比喩的な一行がある。バルトを直接知っていた者ならではの表現である。バルトの身体に接していた者だから「あの声のきめ」と書けたのである。パリ留学中に講義を聞いた松浦寿輝さんはバルトの声について、ラカン(「降ってくる言葉を、一語一語ご託宣として途切れ途切れに呟く」)やフーコー(「華やかなレトリックで飾られた言論で人々を眩惑する」)と比べながら「滑らかで深々とした、聞いていてとても心地よい声なんですが、他人の声を呼び込む余地を残しているような声であり喋り方なんです」と語っている。
つぎに、聞き手について。この本に収録された38本のインタビューの末尾に掲載媒体と聞き手の名が記されている。その中で抜きん出ている一本が、1972年の「快楽/エクリチュール/読解」で、聞き手はジャン・リスタ。1943年生まれだからまだ20代のリスタが、ほとんど父親世代のバルトに、『サド、フーリエ、ロヨラ』に関して、的確な引用にもとづくジャブのような質問を繰り出して行く。それに応じるバルトは押したり引いたり真剣に答えている。これが掲載されたのは『レットル・フランセーズ』誌で、その翌月にはジャック・デリダ特集号を出すべく、リスタがバルトに原稿の依頼をした。
バルトは依頼を断ったのだが、断り状がそのまま雑誌に載せられた(「ジャン・リスタへの手紙」、ロラン・バルト著作集8『断章としての身体』所収)。書けない理由を時間と疲労だと謝りながら、自分がデリダとその読者とは別の世代(上の世代)に属すること、デリダの哲学的課題の設定、文学についての発言(アルトー、マラルメ、バタイユ……)は決定的であること、いくつかの新語をデリダに負っていることを簡潔に伝え、こう締めくくっている。「デリダの仕事のなかにはなにかしら口に出されていないものがあって、それがとても魅力的です。彼の孤独は、彼がこれから言おうとしていることに由来するのです」。これにたいするデリダの個人的な礼状が最近になって公開された。バルトとの「近接性、感謝、共犯性をそなえた同じような関係」を結ぶのは、ほかにブランショだけだと、その手紙でデリダは書いている。
デリダといえば、この本の中で『S/Z』がバルト自身にとって重要な本だと語る1971年の発言にも目が留まる。「そこで、確かに、変化を行ったから、自分自身に対してある変化を成し遂げることができたからです。それはしばしば他者からやって来たのです。なぜならわたしの周囲には探究者、「警句家」がいたからです。デリダ、ソレルス、クリステヴァです(もちろん、いつも同じ顔ぶれです)。彼らはわたしに物事を教え、わたしの迷妄をひらき、わたしを説得しました」。発表順に並べられたインタビューを通読すると、この三人がもたらしたものの大きさがよくわかる。
最後にもう一つ。ベルナール=アンリ・レヴィに「あなたはご自分の書いたものを読み直すことがありますか?」と尋ねられて、バルトはこう答えている。「全然ありません。恐ろしいのです。よい作品であれば、もうこんなのは書けない、と思うでしょう。その反対に、悪い作品であれば、それを書いたことを後悔するでしょうから」
文字を通して、バルトの「声のきめ」に触れていただく機会となれば幸いである。
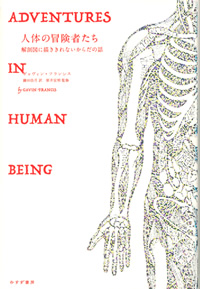
2018.07.23
G・フランシス『人体の冒険者たち――解剖図に描ききれないからだの話』 鎌田彷月訳 原井宏明監修

2018.07.10
[第7回配本・全11巻]