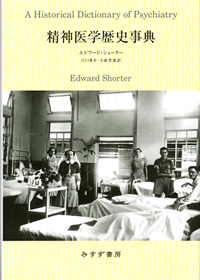舞台はアメリカ東岸の、カナダと国境を接するメイン州ヨーク。「ワイルド・ノール(荒々しい丘)」と呼ばれる厳しい自然に抱かれた海辺の家に、ベルギー生まれのアメリカの作家サートンは、亡くなるまでの二十余年を過ごした。『70歳の日記』を書いたころは、ペットの猫と犬がいっしょだった。
本書を読み進むと、思わずハッとしたり、深く共感する文章にたくさん出会う。いくつか拾ってご紹介しよう。
- まず、老いについて。
- 「朗読会で「今が人生で最良のときです。年をとることはすばらしいことですよ」と言ったら、聴衆の一人が、「年をとることのどこがいいのですか?」と大きな声で質問した。反射的にこう答えた――質問者の言葉にそんなはずはないという響きがあったので、ちょっと身構えつつ。「今までの生涯で、いちばん自分らしくいられるからです」」
- 「若い友人たちからみれば、70歳なんてものすごいおばあさんだと思うのだろうが、実際には6年前に『海辺の家』を書いたときより今のほうが、ずっと若い気がしている」
- 「私には、多くてもあと10回か15回の春しか」めぐってこない!「私の生涯はほとんど終わってしまったのだ。でもその半面、私の頭のなかには70回の春があり、それらは今、豊かさとともに甦ってくる」
- つぎにサートンにとっての「独り居」の大切さと、庭仕事について。
- 「若い友人を誘ってお昼をいっしょにしたら、翌日の午前中にするはずの仕事に必要な切れ味(エッジ)がなくなってしまった!」
- 「雑草に埋め尽くされた多年草の花壇をきれいにしながら、感覚を研ぎ澄まし、精神の落ち着きを取り戻そう」
- 「最初のクレマチスが咲きはじめた。薄紫の花弁の真ん中に赤い筋が入っている。ここに最初に来たときは、クレマチスがみごとに咲き乱れていたけれど、その後は苦戦している。庭にはつねに、いくつもの失敗とひと握りの成功とが同居している――まるで人生そのもののように」
- しかし友人との交流は、生活のいちばん大切な部分でもある。
- 「80代が人生でいちばん幸せだと言ってのける人といっしょにいるのは、ほんとうに楽しい。しかも彼女は車に乗っているときは何もしゃべらない。目に見えるものに集中したいからという」
- 「ベッツィはコートも持たずに来たけれど、手土産にはとてつもなく高価なシャンパンとレコード、そして私にサインしてもらうための本を何冊か持ってきた。たぶん彼女もその友人たちも、ろくに食べるものも食べていないのではないだろうか。朝食は抜き、お昼もめったに食べず、グラノーラで生き延びているのでは。それにひきかえ、私はなんと年をとり、ブルジョアな生活をしていることか!」
- 読者が訪ねてくると、サートンは思う――本で知っているだけの作家に、実際に会おうとやってくる人たちが出会うのは、「愚かさも葛藤もいっぱい抱え、家の雑事に悩まされ、いつも親切とはかぎらない、ごく平凡な人間」だと。
- 最後に読書から。
- 「コルベ神父の場合には、どんな苦しみにも、飢えによる死でさえも消すことのできない光があふれていたことが感じられる。途切れることのない旺盛な慈悲心があったからこそ、……彼は他者を助けることをやめなかった。そして揺るぎない信仰心があったからこそ、平静を保ち、光のなかで生きることができた」
- イサク・ディネセンの自伝を読んでから、「彼女のスノビズムがW・B・イェイツのそれに似ていることに気づいた。物質主義的な中産階級とはけっして相容れないが、貴族や農民階級とはつながりをもてる能力である」
永らく待たれた久しぶりのサートンの一冊。彼女は「そのきりりと背筋の伸びた姿で私たちを勇気づけ、魅了してやまない」(訳者あとがき)。