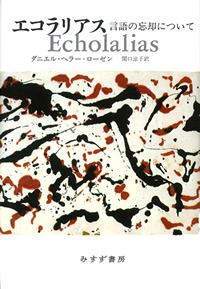
2018.06.08
好評、ヘラー=ローゼン『エコラリアス』 巻末「解説」よりウェブ転載
『エコラリアス――言語の忘却について』 関口涼子訳
『ロラン・バルトによるロラン・バルト』 石川美子訳
2018.05.25
ロラン・バルトは、1973年夏から少しずつ書きためてきた本を、1974年9月3日に書き終える。そしてその本は、1975年2月に『ロラン・バルトによるロラン・バルト』というタイトルで刊行された。以前には「作者の死」を語っていたバルトが、自伝的な作品を出したことは大きな話題となり、2月14日付の『ル・モンド』紙は2ページにわたる大書評で「バルトはどこへ進んだのか。自分自身へだ」と論じた。
この本の発端は、版元のスイユ社が主催した昼食会の席上だったとバルトがインタビューで明かしている。「一人の作家にいつか自作の批評をするよう求めてみるのは興味深いだろうということで、皆の意見が一致しました。この本はそのような精神において、自己の二重化がはらむ種々の気晴らしをそっくり許容するような一種のギャグとして、わたし自身の模作として、構想したものです。」(中地義和訳)
かつて「永遠の作家」というシリーズで『ミシュレ』を書いたバルトに、同じ形式で『バルト』を書かせてみる(*)。パロディの遊戯として企画された本だったが、仕事を始めたバルトはそんな「遊び」がつまらなく思えてきた。そこでこの機会を利用して、自分にとっての「想像界」を演出し、知性をめぐる一種の小説を書こうと考えるようになった。
「この小説は『真実』でしょうか。そこでわたしが口にすることは、ほんとうにわたしの考えていることでしょうか。それを考える『わたし』とは何者でしょうか。一つのイメージでしょうか。周知のように、想像界とは、無意識とイデオロギーと呼ばれる二つの新しい力に関する無知そのものです。ある意味でわたしの本は『愚か』です。わかっていながらそれには言及しません。まるでわたしがわたし自身のプヴァールとぺキュシェであるかのようです。」(同上)
原書から4年後に小社で刊行した、初訳の『彼自身によるロラン・バルト』のあとがきで訳者の佐藤信夫は、この本の内容を粗雑に要約することを避けながら、翻訳の難しかったロラン・バルトをこう評している。「世間ではとかく両立しない反対の特性となりかねない繊細さと論理性というふたつの感受性を、バルトほど極端にそなえ、それゆえに並はずれた快楽と苦痛を感じないではいられない思考者を、私はほかに知らない。」『記号人間』や『レトリック感覚』の著作によって、佐藤信夫がわが国の読書界に登場してきた頃で、言語哲学者としてのセンスは翻訳にも生かされていた。
それから40年、生誕百年(2015年)を迎えた折の国際シンポジウムのテーマは、過去の理論家としてのバルト再発見ではなく、作家バルトの「未来への遺産」としての確認であった。「絵画」「自伝」「中性」「映像」「愛」「音楽」「モード」「文学」など多様な側面から、バルトの遺したものを各人が受け継ごうとしている。そうした時代の変化に応じ、バルト研究の積み重ねをじゅうぶんに生かした『バルトによるバルト』のこの新訳は、かならずやロラン・バルト体験を一新すると信じている。
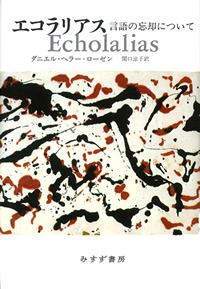
2018.06.08
『エコラリアス――言語の忘却について』 関口涼子訳

2018.05.23
『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』 南條郁子訳