トピックス
北御門二郎『ある徴兵拒否者の歩み』
トルストイに導かれて
終戦から64年を数え、戦争体験は風化の一途をたどっています。そんななか、小社から、数奇な戦争体験をつづった手記『ある徴兵拒否者の歩み』が刊行されます。初版は径書房(1984年)、のち地の塩書房でも刊行されてきた本書が、いっそう広く、永く読み継がれることを願っての新装復刊です。
著者は北御門二郎(1913-2004)。『アンナ・カレーニナ』『イワンの馬鹿』などの生き生きとした訳文で多くの読書人に愛されたトルストイ翻訳家です。
熊本のギリシャ正教の家庭に育った北御門は、旧制高校時代にトルストイと出会い魂を震撼させられました。「トルストイを原文で読むため」にロシア語の習得を立志し、東大英文科に在籍しながら、ロシア語を学ぶためにハルビンに渡りました。そこで知った日本軍の残虐行為に戦慄を覚えた北御門は、トルストイが提唱した絶対平和主義を実践するべく帰国後の日本で徴兵拒否を敢然と行ない、“公然反逆者”という烙印を捺されることとなったのです。
戦争傍観者となり、熊本の山村から戦渦を見つめ続けた青年時代。「誰よりもトルストイの気持がわかる」という矜持からロシア文学の大家に論争を挑み、訳業の道を歩んだ壮年時代。そして、憲法9条を反古にしようとする翼賛的な政治家の言動に心を痛め、それでもなお“殺しあわない世界”の実現を希求し続けた老年時代。その生涯をつづった本書には、ファシズムが蔓延する当時の時代状況においても、自らの良心にしたがい行動する北御門の強靭な精神力が描かれます。
国中が戦争という「殺し合い」を是認し、侵略や残虐行為を繰り返す日本軍の「躍進」に沸きたつなか、独り絶対平和主義を貫くことの困難さは想像を絶します。本書は、トルストイに導かれた北御門の真率なる歩み――もう一つの戦争体験――を知る好機となるのではないでしょうか。
◆姜尚中氏、推薦
「トルストイが理想とした平凡さの中の真の偉大さを体現した稀有な人。誰もが有す不服従の魂に至る一つの解が、ここに在る」。政治学者の姜尚中氏が推薦文をお寄せくださいました。
2009年夏の読書のご案内――戦争体験をつづる手記
北御門二郎『ある徴兵拒否者の歩み』のほかにも、戦争体験を描いた本が数多く、みすず書房から出版されています。

映画監督・小津安二郎は一下士官として中国大陸で従軍し、その後、軍報道部映画班としてシンガポールに赴任。終戦を同地で迎えました。その見聞、思考、体験を伝える貴重な資料がこの本です。いわゆる支那事変のさいの小津の「従軍日記」は、生涯の日記のなかでもっとも緻密・濃密な記述で知られていますが、実はもう一冊残されていたノート「陣中日誌」を、本書に全文公開。このほか大正の少年時代から終戦にいたる新資料を発掘しながら、人間小津の戦争体験を解き明かします。(ちなみに「従軍日記」のほうは『小津安二郎「東京物語」ほか』に収められています。)

著者はオランダ人。高校の理科の教師をしていましたが、第二次世界大戦中、日本軍のジャワ島侵攻と同時に捕虜になり、釜石の収容所に送られます。その日記には、捕虜の輸送や収容所のようす、強制労働のことが詳しく記録されていますが、それにもまして心うたれるのは、極限状況のなかで戦友の病状を気遣い、労働のあいまをぬって化学の教科書をつくり、子どもたちの誕生日に手紙を書きおくる著者の姿です。望郷の念、信仰と平和の大切さを必死に伝えようとするこの本にふれると、人間の尊厳とは何かを考えずにはいられません。

日本に強制連行された中国人男性、日本軍に性的暴力を受けた女性たち――。虜囚にされた人びとは、その後の人生を、抑圧と障害を背負い続けて生きているのです。精神科医の著者は、中国・台湾を訪ね、被害者から体験を丹念に聞き取りました。同じ著者が、もと日本兵だった人びとの体験を聞き取り分析した『戦争と罪責』(岩波書店)と一対で、歴史の証人の言葉を伝え、戦争の罪責を訴えかける貴重なドキュメントです。
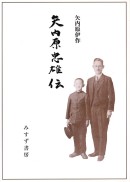
戦後には東京大学総長を務め、大学の自治と学問の自由を毅然と守りぬいた矢内原忠雄は、すぐれた経済学者であり、大学人であり、無教会キリスト者でした。戦前、専門の植民政策を論じてしだいに当局と緊張を深め、民主主義の理念をかかげて廬溝橋事件、南京大虐殺を批判し、教授の職を追放されます。自宅に「土曜学校」を開いて古典を講義し、平和主義を説き続けた矢内原の内面のドラマを、子の伊作が描きます。

いわゆる十五年戦争のもと、国家権力への抵抗はありえたのでしょうか? 大勢順応の時流のなか、信念・信仰を曲げまいとする知識人や庶民の姿勢、それは強権により圧殺される運命にありましたが、しかし抵抗はたしかに存在しました。この全2巻の研究書は、キリスト者・自由主義者を対象に、戦時下におこなわれた抵抗の事例を原文献や聞き取りから探り出し、調査し評価した第一級の資料です。第1巻ではおもに結社・集団の抵抗、第2巻では個人の抵抗の豊富な事例をとりあげています。
「戦後責任」という言葉が重くのしかかる21世紀――。戦争体験を次代に語り継ぐことで、その責任をいくらかでも、背負ってゆくことができはしないでしょうか。
一昨年夏は、フランクル『夜と霧』からホロコーストを知る手がかりになる本へと、昨夏は日本に目を転じてヒロシマ・ナガサキの原爆、核兵器に関連した本へと、読み広げる読書の特集を組んでみました。そちらのページもまたごらんいただけましたら幸いです。
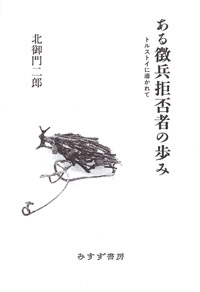
「夏の読書のご案内」
- 2018年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(9)」
エレーナ・ムーヒナ『レーナの日記』 - 2016年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(8)」
G・パウゼヴァング『片手の郵便配達人』
E・ヴィーゼルの訃報と『夜』
V・E・フランクルの新装復刊
月刊『みすず』7月号の2篇より - 2015年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(7)」
S・ヴィレンベルク『トレブリンカ叛乱』近藤康子訳
N・タース『動くものはすべて殺せ』布施由紀子訳 - 2014年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(6)」
野呂邦暢『夕暮の緑の光』『白桃』
山本義隆『世界の見方の転換』全3巻 - 2013年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(5)」
M・オランデール=ラフォン『四つの小さなパン切れ』高橋啓訳 - 2012年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(4)」
G・パウゼヴァング『そこに僕らは居合わせた』高田ゆみ子訳
S・ギルバート『ホロコーストの音楽』二階宗人訳 - 2011年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(3)」
E・ホフマン『記憶を和解のために』早川敦子訳
宮田昇『敗戦三十三回忌』 - 2010年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から(2)」
羅英均『日帝時代、わが家は』小川昌代訳
ノーマ・フィールド『へんな子じゃないもん』大島かおり訳
千田善『戦争はなぜ終わらないか』
T・ガートン・アッシュ『ファイル』今枝麻子訳
益井康一『漢奸裁判史』[新版]劉傑解説 - 2009年夏のトピックス「北御門二郎『ある徴兵拒否者の歩み』」
北御門二郎『ある徴兵拒否者の歩み』
田中眞澄『小津安二郎と戦争』
E・W・リンダイヤ『ネルと子どもたちにキスを』村岡崇光監訳
野田正彰『虜囚の記憶』
矢内原伊作『矢内原忠雄伝』
同志社大学人文科学研究所編『戦時下抵抗の研究』全2巻 - 2008年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』から」
大石又七『ビキニ事件の真実』
M・ハーウィット『拒絶された原爆展』山岡清二監訳
ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』大島かおり訳
F・ダイソン『科学の未来』はやし・はじめ/はやし・まさる訳
『仁科芳雄』玉木英彦・江沢洋編
朝永振一郎著作集 4 『科学と人間』/5 『科学者の社会的責任』 - 2007年夏のトピックス「フランクル『夜と霧』」
【ホロコーストを知るには、フランクルについて知るには】
ブルッフフェルド/レヴィーン『語り伝えよ、子どもたちに』高田ゆみ子訳
F・ティフ編著『ポーランドのユダヤ人』阪東宏訳
E・リンゲルブルムの『ワルシャワ・ゲットー』大島かおり訳
E・ヴィーゼル『夜』村上光彦訳
I・カツェネルソン『滅ぼされたユダヤの民の歌』飛鳥井・細見訳
R・クリューガー『生きつづける』鈴木仁子訳
H・クリングバーグ・ジュニア『人生があなたを待っている』全2巻 赤坂桃子訳
V・E・フランクル『死と愛』霜山徳爾訳
『フランクル・セレクション』全5冊