トピックス
シリーズ《始まりの本》
[最新刊](2014年1月24日)
始まりとは始原(オリジン)。
新たな問いを発見するために、いったん始原へ立ち帰って、
これから何度でも読み直したい現代の古典。
未来への知的冒険は、ふたたびここから始まる。
* 2014年1月24日配本 (2冊)
『ヒステリーの発明――シャルコーとサルペトリエール写真図像集』


ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 谷川多佳子・和田ゆりえ訳 上・下
- ――今日われわれに、『サルペトリエール写真図像集』が残されている。すべてがそこにある――ポーズ、発作、叫び、「熱情的態度」、「苦悩」、「恍惚」、あらゆる錯乱の姿態。写真のもたらすシチュエーションが、ヒステリーの幻影と知の幻影との絆を理想的に結晶させたがゆえに、すべてがそこに有るように見える。呪縛の相互作用が定着したのだ。すなわち、「ヒステリー」の映像を飽かず求めつづける医師たち――従順に身体の演劇性を増幅していくヒステリー患者たち。こうしてヒステリーの臨床医学はスペクタクルになった。〈ヒステリーの発明〉だ。それは暗々裡に、芸術にも比すべきものに自らを同一化していった。演劇や、絵画とも紛うものに。――
- ――フロイトは催眠のプロセスを、多大な教導権をもつがゆえに自我理想となるにいたるひとりの「主人」を前にした、患者の「恋による全面的自己放棄」として描き出した。とりわけこうした理由から、催眠術師に命令されるや、現実吟味そのもの(私はほんとうは小鳥でも蛇でもなく、僧侶でも、女優でさえもない……)が挫折する。この機会にフロイトは、恋愛状態から催眠へ、さらには集団構造へ、最終的には神経症へといたる、点線ではあるが揺るぎのないラインを引いたのであった。彼は催眠をあるときは愛、またあるときは魔術として語るが、ほとんどの場合それを暴力として捉えている。それは呪縛と残酷さの中間にある技術についての一観念なのである。――
- ジャネ『症例 マドレーヌ』松本雅彦訳はこちら
- ジャネ『被害妄想』松本雅彦訳はこちら
- ジャネ『解離の病歴』松本雅彦訳はこちら
- ジャネ『心理学的自動症』松本雅彦訳はこちら
- ランク『出生外傷』細澤・安立・大塚訳はこちら
- オプホルツァー『W氏との対話』馬場・高砂訳はこちら
- 『現代フロイト読本』 1 西園昌久監修・北山修編集代表はこちら
- 『現代フロイト読本』 2 西園昌久監修・北山修編集代表はこちら
- 西丸四方『精神医学の古典を読む』はこちら
- 中井久夫『西欧精神医学背景史』はこちら
- ラプランシュ/ポンタリス『精神分析用語辞典』村上仁監訳はこちら
- デュフレーヌ『〈死の欲動〉と現代思想』遠藤不比人訳はこちら
- サンダース『ポスト・クライン派の精神分析』平井正三序・中川慎一郎監訳はこちら
- デリダ『盲者の記憶』鵜飼哲訳はこちら
- ド・セルトー『ルーダンの憑依』矢橋透訳はこちら
- フーコー『臨床医学の誕生』神谷美恵子訳・斎藤環解説《始まりの本》はこちら
- アッカークネヒト『パリ、病院医学の誕生』舘野之男訳・引田隆也解説《始まりの本》はこちら
* 2013年8月23日配本 (1冊)
『ケアへのまなざし』

神谷美恵子 外口玉子解説
- ――弱者に対する強者の優越感というものは医療の場では極めて起こりやすいことで、しかも強者自身は案外気づいていないことが多いのではなかろうか。医療者も一度病人という弱者になってみるのが一ばん手っ取り早く、このことに気づく道かもしれないが、みんなにこの道をとられても困る。だから唯一の可能な道は「自分もまた病みうる者だ」「自分もまた死にうる者だ」ということを、絶えず念頭においておくことだろう。 もうひとつ医療者が知らず知らず持ちやすい思いあがりの心は、「患者の心は何もかもよくわかっている」と思い込んでしまうことだろう。――
- 『神谷美恵子コレクション』全5冊はこちら
- フーコー『臨床医学の誕生』神谷美恵子訳《始まりの本》はこちら
- 宮﨑かづゑ『長い道』はこちら
- 近藤宏一『闇を光に――ハンセン病を生きて』はこちら
- 斉藤道雄『悩む力――べてるの家の人びと』はこちら
- 斉藤道雄『治りませんように――べてるの家のいま』はこちら
- 中井久夫『統合失調症の有為転変』はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談』はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談 続』はこちら
- ドゥーリー/マッカーシー『看護倫理』1 坂川雅子訳はこちら
- ドゥーリー/マッカーシー『看護倫理』2 坂川雅子訳はこちら
- ドゥーリー/マッカーシー『看護倫理』3 坂川雅子訳はこちら
- 岡野八代『フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ』はこちら
* 2013年6月25日配本 (2冊)
『ベンヤミン/アドルノ往復書簡 1928-1940』
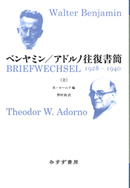
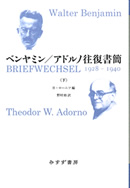
H・ローニツ編 野村修訳 森田團解説 上・下
- ――もう一度強調させていただきたいのは、「祈り」としての「注意深い心づかい」の重要性です。あなたの書かれたもののうちで、これにまさって重要なものはあるまい、あなたの内奥の諸モティーフについて、これほど厳密に解き明かしてくれるものは、ほかにはあるまい。(アドルノからベンヤミンへ)
ぼくはきみの手紙を、たんに読んだのではなく、研究した。あの手紙の一語一語が、熟考を求めてくる。きみがぼくの志向をきわめて正確に捉えているだけに、きみによる欠陥の指摘は、大いに重みをもつ。(ベンヤミンからアドルノへ)―― - ――出口のない状況にあって、ぼくはそれに、けりをつけるほかなくなっている。ぼくが生を終えようとしているのは、誰ひとりとしてぼくを知る者のいない、ピレネー山中の小さな村のなかだ。あなたにお願いするが、ぼくの思いをぼくの友人のアドルノに伝え、ぼくが置かれることとなった状況を、かれに説明してやってほしい。書ければ書きたかった手紙という手紙を書くだけの時間が、ぼくには残されていないのだ。(ベンヤミン最期のアドルノへの伝言)――
- 『アドルノ 文学ノート』 1 三光長治他訳はこちら
- 『アドルノ 文学ノート』 2 三光長治他訳はこちら
- アドルノ『キルケゴール』山本泰生訳はこちら
- アドルノ『哲学のアクチュアリティ』細見和之訳《始まりの本》はこちら
- 細見和之『アドルノの場所』はこちら
- ローゼンツヴァイク『救済の星』村岡・細見・小須田訳はこちら
- ブーレッツ『20世紀ユダヤ思想家』 1 合田正人他訳[全3巻]はこちら
- ウィルソン『フィンランド駅へ』 上 岡本正明訳はこちら
- ウィルソン『フィンランド駅へ』 下 岡本正明訳はこちら
- ジェイ『弁証法的想像力』荒川幾男訳はこちら
- グラムシ『知識人と権力』上村忠男訳はこちら
- 『ミレナ 記事と手紙――カフカから遠く離れて』松下たえ子編訳はこちら
- カツェネルソン『滅ぼされたユダヤの民の歌』飛鳥井・細見訳はこちら
- マン『ワーグナーと現代』小塚敏夫訳はこちら
- リース『フルトヴェングラー――音楽と政治』八木・芦津訳はこちら
- 奥波一秀『クナッパーツブッシュ――音楽と政治』はこちら
* 2013年4月10日配本 (1冊)
『ロシア革命の考察』

E・H・カー 南塚信吾訳
- ――レーニンは、説得とか教化というものは、それを受ける人々の心に合理的な確信を植えつけようとするものであるという意味において、それを合理的な過程とみなした。スターリンは、それが合理的なエリートによって計画されそして行なわれるという意味においてのみ、それを合理的な過程とみなした。その目的は、多数の人々を一定の望ましい行動に向けて誘導することであった。(…)しかし、この目的を達成するさいに用いるべき最も有効な方法は、必ずしも、つねにまたはしばしば、理性にかなうものではなかった。――
- カー『ナショナリズムの発展』大窪愿二訳はこちら
- クリヴィツキー『スターリン時代』根岸隆夫訳はこちら
- ネイマーク『スターリンのジェノサイド』根岸隆夫訳はこちら
- ザスラフスキー『カチンの森』根岸隆夫訳はこちら
- ザヴォドニー『消えた将校たち』中野・朝倉訳 根岸隆夫解説はこちら
- リード/フィッシャー『ヒトラーとスターリン』上 根岸隆夫訳はこちら
- リード/フィッシャー『ヒトラーとスターリン』下 根岸隆夫訳はこちら
- 武藤洋二『天職の運命』はこちら
- ビーヴァー『スペイン内戦』上 根岸隆夫訳はこちら
- ビーヴァー『スペイン内戦』下 根岸隆夫訳はこちら
- ジョル『ヨーロッパ100年史』 1 池田清訳はこちら
- ジョル『ヨーロッパ100年史』 2 池田清訳はこちら
- ノイマン『大衆国家と独裁』岩永・岡他訳訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』1 大久保和郎訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』2 大島通義・大島かおり訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』3 大久保和郎・大島かおり訳はこちら
* 2013年2月21日配本 (2冊)
『孤独な群衆』


デイヴィッド・リースマン 加藤秀俊訳 上・下
- ――この本でとりあつかうのは、社会的性格と、ことなった地域、時代、集団にぞくする人間の社会的性格の相違についてである。われわれは、いったん社会のなかにできあがったことなった社会的性格が、その社会での労働、あそび、政治、そして育児法などのなかに展開してゆく仕方をかんがえてみたいとおもう。そしてとりわけ、十九世紀のアメリカの基調をなしたひとつの社会的性格が、まったくべつな社会的性格にだんだんと置きかえられてきている事情を、この本では問題にしてみたい。なぜ、こうした変化がおきたのか。どんなふうにこの変化はおきたのか。――
- ――もしも、他人指向的な人間がじぶんがいかに不必要な仕事をしているか、そして、じぶんじしんの考えだの、生活だのというのがそれじしん他人たちのそれとおなじようにじつに興味深いものであるということを発見するならば、かれらはもはや群衆のなかの孤独を仲間集団に頼らないでもすむようになるであろう。人間はそれぞれの個人の内部に汲めどもつきない可能性をもっているのだ。そのような状態になったとき、人間はじぶんじしんの実感だの、抱負だのにより多くの関心をはらうようになるにちがいない。――
- ベラー『心の習慣――アメリカ個人主義のゆくえ』中村圭志訳はこちら
- ベラー他『善い社会――道徳的エコロジーの制度論』中村圭志訳はこちら
- ホール『かくれた次元』日高・佐藤訳はこちら
- モラン『オルレアンのうわさ』杉山光信訳はこちら
- ブルデュ『実践感覚』 1 今村・港道訳はこちら
- ブルデュ『実践感覚』 2 今村仁司他訳はこちら
- マッキンタイア『美徳なき時代』篠崎榮訳はこちら
- ウォリン『政治学批判』千葉眞他編訳はこちら
- ウォリン『アメリカ憲法の呪縛』千葉眞他訳はこちら
- ガウスタッド『アメリカの政教分離』大西直樹訳はこちら
- メナンド『メタフィジカル・クラブ』野口良平他訳はこちら
- 松本礼二『トクヴィルで考える』はこちら
- マクルーハン『メディア論』栗原・河本訳はこちら
- マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』森常治訳はこちら
* 2013年1月7日配本 (1冊)
『サリヴァン、アメリカの精神科医』

中井久夫
- ――現在の精神医学は症状によって診断し、その症状の薬物による撲滅を第一とする。統合失調症の診断を狭くしたのは病名にからむスティグマを考慮したといっても、それはスティグマを負う人数を減らしたにすぎない。患者をまず症状によって評価し分類し特徴づけることは、患者をそのもっとも影の部分によって評価することである。これは患者の自己評価を落とし、自己尊敬を空洞化し、陰に陽に慢性状態成立に貢献しているであろう。これに対してまず人柄を問うサリヴァンの方法は、モラル・トリートメントの伝統に立つものである。有効な薬物があらわれたことは、この伝統を不要にすることではない。むしろ、ますますそれが要請される事態である。――
- サリヴァン『現代精神医学の概念』中井・山口訳はこちら
- サリヴァン『精神医学の臨床研究』中井・山口他訳はこちら
- サリヴァン『精神医学的面接』中井久夫他訳はこちら
- サリヴァン『精神医学は対人関係論である』中井久夫他訳はこちら
- サリヴァン『分裂病は人間的過程である』中井久夫他訳はこちら
- クヴァーニス/パーロフ編『サリヴァンの精神科セミナー』中井久夫訳はこちら
- ペリー『サリヴァンの生涯』 1 中井・今川訳はこちら
- ペリー『サリヴァンの生涯』 2 中井・今川訳はこちら
- クッファー他編『DSM-V研究行動計画』黒木・松尾・中井訳はこちら
- 中井久夫『徴候・記憶・外傷』はこちら
- 中井久夫『最終講義――分裂病私見』はこちら
- 中井久夫『統合失調症』 1《精神医学重要文献シリーズHeritage》はこちら
- 中井久夫『統合失調症』 2《精神医学重要文献シリーズHeritage》はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談』はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談 続』はこちら
* 2012年12月25日配本 (1冊)
『物理学への道程』

朝永振一郎 江沢洋編
- ――自分のようなものが大それた学問などやろうと思ったのは結局やっぱりまちがいだった、といった想念がいつも心の底にこびりついている。そんなとき、東山荘の朝の礼拝から聞こえてくる讃美歌の甘美な声に意味もなく涙ぐんでみたり、そうかと思うと、その礼拝の蜜豆のような甘いだけのムードに反発を感じてみたり、」そしてあたりの自然がみずみずしく美しければ美しいで、物理学的自然などという灰色の世界をいじくりまわすことの何と空虚なわざであることよ、などと言いたくなってきたりする。しかしそれと同時にこんなことを言う自分が、イソップの「すっぱい葡萄」に登場する狐のようにひねくれた人間に見えてきたりする。(「思い出ばなし」より)――
- 朝永振一郎『プロメテウスの火』《始まりの本》はこちら
- 『朝永振一郎著作集』はこちら
- 朝永振一郎編『物理学読本』[第2版]はこちら
- 朝永振一郎『量子力学』 I [第2版]はこちら
- 朝永振一郎『量子力学』 II [第2版]はこちら
- 朝永振一郎『角運動量とスピン』亀淵・原・小寺編はこちら
- 朝永振一郎『新版 スピンはめぐる』江沢洋・注はこちら
- 朝永振一郎『庭にくる鳥』はこちら
- ハイゼンベルク『部分と全体』山崎和夫訳 湯川秀樹序文はこちら
- ハイゼンベルク『現代物理学の思想』河野・富山訳はこちら
- ハイゼンベルク『現代物理学の自然像』尾崎辰之助訳はこちら
- ハイゼンベルク『自然科学的世界像』[第2版]田村松平訳はこちら
- ボーア『原子理論と自然記述』井上健訳はこちら
- ボーム『量子論』高林・井上・河辺・後藤訳はこちら
- ボルン『現代物理学』鈴木・金関訳はこちら
- ローズ『角運動量の基礎理論』山内・森田訳はこちら
- ファインマン/ヒッブス『量子力学と経路積分』北原和夫訳はこちら
- ディラック『量子力学』[第4版][リプリント版]
Dirac, THE PRINCIPLES OF QUANTUM MECHANICS, FOURTH EDITION
* 2012年12月21日配本 (1冊)
『パリ、病院医学の誕生――革命暦第三年から二月革命へ』

E・H・アッカークネヒト 舘野之男訳 引田隆也解説
- ――当時の医学は、私たち現代の「研究室医学」とはちがっていたし、また古代の「ベッドサイド医学」でもなかった。〔…〕この55年間には、その主要な要素にちなんで私たちが「病院医学」と名づけた、まったく特殊で独特な型の医学が起こったのである。〔…〕 病院を廃止しようとしたこの革命は、病院を改善し、医学の中心とした。公の医学教育を廃止しようとしたこの革命は、新しい非常に強力な医学教育を創造した。医学の廃止を夢みたこの革命は、医学の新時代を開いた。(本文より)――
- ――解剖学のまなざしと臨床医学のまなざし、すなわち病理解剖学の屍体空間と臨床医学の病の時間とは、元来、地理と歴史の相違として、対立する構造をもっているからである。屍体空間と病の時間という異質なものが重なりあうことこそ、「臨床医学の誕生」の秘密であり、「病院医学の誕生」の秘密なのである。『パリ、病院医学の誕生』を『臨床医学の誕生』と重ねて「読む」意義は、そこにある。(解説より)――
- フーコー『臨床医学の誕生』《始まりの本》はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 1 はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 2 はこちら
- ロッシ『魔術から科学へ』前田達郎訳はこちら
- 中井久夫『西欧精神医学背景史』はこちら
- ウィルソン『フィンランド駅へ――革命の世紀の群像』上 岡本正明訳はこちら
- ウィルソン『フィンランド駅へ――革命の世紀の群像』下 岡本正明訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 1 河野・阪上・富永監訳こちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 2 河野・阪上・富永監訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 3 河野・阪上・富永監訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 4 河野・阪上・富永監訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 5 河野・阪上・富永監訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 6 河野・阪上・富永監訳はこちら
- フュレ/オズーフ編『フランス革命事典』 7 河野・阪上・富永監訳はこちら
* 2012年11月1日配本 (1冊)
『カフカとの対話――手記と追想』

グスタフ・ヤノーホ 吉田仙太郎訳 三谷研爾解説
- 『カフカ自撰小品集』《大人の本棚》吉田仙太郎訳はこちら
- 『ミレナ 記事と手紙――カフカから遠く離れて』松下たえ子編訳はこちら
- 高橋悠治『カフカノート』はこちら
- 高橋悠治『カフカ/夜の時間――メモ・ランダム』はこちら
- ツィシュラー『カフカ、映画に行く』瀬川裕司訳はこちら
- 三原弟平『カフカ『断食芸人』〈わたし〉のこと』《理想の教室》はこちら
- 池内紀の仕事場 3『カフカを読む』はこちら
- 小岸昭『マラーノの系譜』はこちら
- 『ヴァルザーの詩と小品』《大人の本棚》飯吉光夫編訳はこちら
- アッペルフェルド『不死身のバートフス』《lettres》武田尚子訳はこちら
- アッペルフェルド『バーデンハイム1939』《lettres》村岡崇光訳はこちら
- 『アドルノ 文学ノート』 1 三光長治他訳はこちら
- 『アドルノ 文学ノート』 2 三光長治他訳はこちら
- [連載]保坂和志「試行錯誤に漂う」月刊『みすず』はこちら
* 2012年9月10日配本 (1冊)
『隠喩としての病い/エイズとその隠喩』

スーザン・ソンタグ 富山太佳夫訳
- ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』北條文緒訳はこちら
- ソンタグ『土星の徴しの下に』富山太佳夫訳はこちら
- ソンタグ『書くこと、ロラン・バルトについて――エッセイ集1/文学・映画・絵画』富山太佳夫訳はこちら
- ソンタグ『サラエボで、ゴドーを待ちながら――エッセイ集2/写真・演劇・文学』富山太佳夫訳はこちら
- クラインマン他『他者の苦しみへの責任――ソーシャル・サファリングを知る』坂川雅子訳 池澤夏樹解説はこちら
- クラインマン『精神医学を再考する』江口重幸他訳はこちら
- P・ファーマー『権力の病理 誰が行使し誰が苦しむのか――医療・人権・貧困』豊田英子訳 山本太郎解説はこちら
- 柘植あづみ『生殖技術――不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか』はこちら
- マーガレット・ロック『脳死と臓器移植の医療人類学』坂川雅子訳はこちら
- マーガレット・ロック『更年期』江口・山村・北中訳はこちら
- フェイドン/ビーチャム『インフォームド・コンセント』酒井・秦訳はこちら
- D・ヒーリー『抗うつ薬の功罪』田島治監修 谷垣暁美訳はこちら
- 『ヒーリー精神科治療薬ガイド』[第5版]田島・江口監訳 冬樹純子訳はこちら
- レネー・C・フォックス『生命倫理をみつめて』中野真紀子訳はこちら
* 2012年6月22日配本 (2冊)
『プロメテウスの火』

朝永振一郎 江沢洋編 [好評重版]
- 『朝永振一郎著作集』はこちら
- 朝永振一郎『量子力学』 I [第2版]はこちら
- 朝永振一郎『量子力学』 II [第2版]はこちら
- 朝永振一郎『角運動量とスピン』亀淵・原・小寺編はこちら
- 朝永振一郎『新版 スピンはめぐる』江沢洋・注はこちら
- 『回想の朝永振一郎』松井巻之助編はこちら
- 『仁科芳雄往復書簡集』全3巻・補巻1はこちら
- 『仁科芳雄』玉木英彦・江沢洋編はこちら
- 山本義隆『福島の原発事故をめぐって――いくつか学び考えたこと』はこちら
- 池内了『科学者心得帳』はこちら
- ダイソン『叛逆としての科学』柴田裕之訳はこちら
- ウィットベック『技術倫理』 1 札野順・飯野弘之訳はこちら
- ハイゼンベルク『部分と全体』山崎和夫訳 湯川秀樹序文はこちら
- パイス『ニールス・ボーアの時代』1 西尾成子他訳はこちら
- パイス『ニールス・ボーアの時代』2 西尾成子他訳はこちら
- マイヤー=アービッヒ『自然との和解への道』上 山内廣隆訳はこちら
- マイヤー=アービッヒ『自然との和解への道』下 山内廣隆訳はこちら
- ラートカウ『自然と権力――環境の世界史』海老根剛・森田直子訳はこちら
『科学史の哲学』

下村寅太郎
[加藤尚武解説]
- コイレ『プラトン』川田殖訳はこちら
- コリングウッド『自然の観念』平林・大沼訳はこちら
- カッシーラー『認識問題』 1 須田・宮武・村岡訳はこちら
- カッシーラー『認識問題』 2-1 須田・宮武・村岡訳はこちら
- カッシーラー『認識問題』 2-2 須田・宮武・村岡訳はこちら
- カッシーラー『認識問題』 4 山本・村岡訳はこちら
- カッシーラー『カントの生涯と学説』門脇・高橋・浜田監修はこちら
- ユクスキュル『動物の環境と内的世界』前野佳彦訳はこちら
- ギリスピー『客観性の刃――科学思想の歴史[新版]』島尾永康訳はこちら
- ヴァン・デル・ウァルデン『数学の黎明』村田・佐藤訳はこちら
- ボホナー『科学史における数学』村田全訳はこちら
- リンドバーグ/ナンバーズ『神と自然』渡辺正雄監訳はこちら
- ドッブズ『錬金術師ニュートン』大谷隆昶訳はこちら
- ロッシ『魔術から科学へ』前田達郎訳はこちら
- クーン『科学革命の構造』中山茂訳はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 1 はこちら
- 山本義隆『一六世紀文化革命』 2 はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 1 はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 2 はこちら
- 山本義隆『磁力と重力の発見』 3 はこちら
* 2012年6月8日配本 (3冊)
『チーズとうじ虫』
16世紀の一粉挽屋の世界像
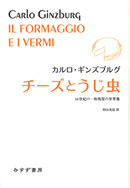
カルロ・ギンズブルグ 杉山光信訳
[上村忠男解説]
- ギンズブルグ『ピエロ・デッラ・フランチェスカの謎』森尾総夫訳はこちら
- ギンズブルグ『歴史を逆なでに読む』上村忠男訳はこちら
- ギンズブルグ『糸と痕跡』上村忠男訳はこちら
- アリエス『〈子供〉の誕生』杉山光信・杉山美恵子訳はこちら
- セルトー『ルーダンの憑依』矢橋透訳はこちら
- カントロヴィッチ『祖国のために死ぬこと』甚野尚志訳はこちら
- ブロック『封建社会』1 新村・森岡・大高・神沢訳はこちら
- ブロック『封建社会』2 新村・森岡・大高・神沢訳はこちら
- ブローデル『日常性の構造』1 《物質文明・経済・資本主義》I-1 村上光彦訳はこちら
- ブローデル『日常性の構造』2 《物質文明・経済・資本主義》I-2 村上光彦訳はこちら
- ブローデル『交換のはたらき』1 《物質文明・経済・資本主義》II-1 山本淳一訳はこちら
- ブローデル『交換のはたらき』2 《物質文明・経済・資本主義》II-2 山本淳一訳はこちら
- ブローデル『世界時間』1 《物質文明・経済・資本主義》III-1 村上光彦訳はこちら
- ブローデル『世界時間』2 《物質文明・経済・資本主義》III-2 村上光彦訳はこちら
- ブローデル『地中海世界』神沢栄三訳はこちら
- デーヴィス『贈与の文化史』宮下志朗訳はこちら
- ロッシ『魔術から科学へ』前田達郎訳はこちら
- アポストリデス『機械としての王』水林章訳はこちら
- スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』上村忠男訳はこちら
- グラムシ『知識人と権力』上村忠男訳はこちら
『政治的ロマン主義』
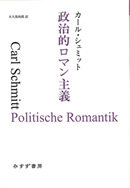
カール・シュミット 大久保和郎訳
[野口雅弘解説]
- シュミット『憲法論』阿部照哉・村上義弘訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』1 大久保和郎訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』2 大島通義・大島かおり訳はこちら
- アーレント『全体主義の起原』3 大久保和郎・大島かおり訳はこちら
- アーレント『過去と未来の間』引田隆也・齋藤純一訳はこちら
- ノイマン『大衆国家と独裁』岩永・岡・高木訳はこちら
- ノイマン『ビヒモス――ナチズムの構造と実際 1933-1944』岡本・小野・加藤訳はこちら
- ミル『ベンサムとコウルリッジ』松本啓訳はこちら
- 関口正司『自由と陶冶――J・S・ミルとマス・デモクラシー』はこちら
- バーク『フランス革命の省察』半澤孝麿訳はこちら
- 中野好之『評伝バーク』はこちら
- 松本礼二『トクヴィルで考える』はこちら
- ヴェーバー『宗教社会学論選』大塚久雄・生松敬三訳はこちら
- 野口雅弘『闘争と文化』はこちら
- 藤田省三『天皇制国家の支配原理』《始まりの本》はこちら
- ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』[増補版]大島かおり訳《始まりの本》はこちら
- 原武史『可視化された帝国』[増補版]《始まりの本》はこちら
『望郷と海』

石原吉郎
[岡真理解説]
- 『長谷川四郎 鶴/シベリヤ物語』小沢信男編《大人の本棚》はこちら
- 高杉一郎『あたたかい人』太田哲男編はこちら
- 新城郁夫『沖縄を聞く』はこちら
- 宮田昇『敗戦三十三回忌』はこちら
- リンダイヤ『ネルと子供たちにキスを』村岡崇光監訳はこちら
- フランクル『夜と霧』[新版] 池田香代子訳はこちら
- フランクル『夜と霧』霜山徳爾訳はこちら
- フランクル『死と愛』霜山徳爾訳はこちら
- ヴィーゼル『夜』村上光彦訳[新版]はこちら
- リンゲルブルム『ワルシャワ・ゲットー』大島かおり訳[新版]はこちら
- ティフ編著『ポーランドのユダヤ人』阪東宏訳はこちら
- ホフマン『記憶を和解のために』早川敦子訳はこちら
- ブルッフフェルド/レヴィーン『語り伝えよ、子どもたちに』高田ゆみ子訳はこちら
- カツェネルソン『滅ぼされたユダヤの民の歌』飛鳥井・細見訳はこちら
- 岡真理『アラブ、祈りとしての文学』はこちら
- ゴイティソーロ『嵐の中のアルジェリア』山道佳子訳はこちら
- ザスラフスキー『カチンの森』根岸隆夫訳はこちら
- ビーヴァー『スペイン内戦』上 根岸隆夫訳はこちら
- ビーヴァー『スペイン内戦』下 根岸隆夫訳はこちら
- グロスマン『人生と運命』1 齋藤紘一訳はこちら
- グロスマン『人生と運命』2 齋藤紘一訳はこちら
- グロスマン『人生と運命』3 齋藤紘一訳はこちら
* 2012年4月配本 (2冊)
『ノイズ』
音楽/貨幣/雑音

ジャック・アタリ 金塚貞文訳
[陣野俊史解説]
- アタリ『カニバリスムの秩序』金塚貞文訳はこちら
- ツヴァイク『昨日の世界』 1 原田義人訳はこちら
- ツヴァイク『昨日の世界』 2 原田義人訳はこちら
- ガタリ『アンチ・オイディプス草稿』ナドー編/國分功一郎・千葉雅也訳はこちら
- レヴィ=ストロース『神話論理』全5冊 吉田禎吾・早水洋太郎・渡辺公三・木村秀雄他訳はこちら
- ジャック・デリダの本はこちら
- グレン・グールドの本はこちら
- 『ロラン・バルト著作集』全10巻[既刊9]はこちら
- クラーゲス『リズムの本質』杉浦實訳はこちら
- サイード『音楽のエラボレーション』大橋洋一訳はこちら
- シェル『芸術と貨幣』小澤博訳はこちら
- 宇野邦一『映像身体論』はこちら
- マクルーハン『メディア論』栗原裕・河本仲聖訳はこちら
- ロス『20世紀を語る音楽』 1 柿沼敏江訳はこちら
- ロス『20世紀を語る音楽』 2 柿沼敏江訳はこちら
- ローズ『ブラック・ノイズ』新田啓子訳はこちら
- グレイ『わらの犬』池央耿訳はこちら
- フーコー『臨床医学の誕生』神谷美恵子訳・斎藤環解説《始まりの本》はこちら
- アドルノ『哲学のアクチュアリティ』細見和之訳《始まりの本》はこちら
- ステント『進歩の終焉』渡辺格他訳・木田元解説《始まりの本》はこちら
『素足の心理療法』

霜山徳爾
[妙木浩之解説]
- フランクル『夜と霧』霜山徳爾訳はこちら
- フランクル『夜と霧』[新版] 池田香代子訳はこちら
- フランクル『死と愛』霜山徳爾訳はこちら
- 『フランクル・セレクション』全5巻はこちら
- ボス『東洋の英知と西欧の心理療法』霜山徳爾・大野美都子訳はこちら
- 木村敏『関係としての自己』はこちら
- 西丸四方『精神医学の古典を読む』はこちら
- 笠原嘉『精神科医のノート』はこちら
- 笠原嘉『新・精神科医のノート』はこちら
- 笠原嘉臨床論集『再び「青年期」について』はこちら
- 笠原嘉臨床論集『外来精神医学という方法』はこちら
- 笠原嘉臨床論集『うつ病臨床のエッセンス』はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談』はこちら
- 中井久夫『臨床瑣談 続』はこちら
- 山下格『誤診のおこるとき』〈精神医学重要文献シリーズHeritage〉はこちら
- 竹中星郎『老いの心と臨床』〈精神医学重要文献シリーズHeritage〉はこちら
- ターナー『自傷からの回復』小国綾子訳・松本俊彦監修はこちら
- 本城秀次『乳幼児精神医学入門』はこちら
- 杉林稔『精神科臨床の場所』はこちら
- 阿部惠一郎『精神医療過疎の町から』はこちら
* 2012年1月配本 (2冊)
『天皇制国家の支配原理』

藤田省三
- 藤田省三『現代史断章』はこちら
- 藤田省三『維新の精神』はこちら
- 藤田省三『精神史的考察』はこちら
- 藤田省三『異端論断章』はこちら
- 『藤田省三対話集成』 1 はこちら
- 『藤田省三対話集成』 2 はこちら
- 『藤田省三対話集成』 3 はこちら
- 丸山真男『戦中と戦後の間』はこちら
- 丸山真男『自己内対話』はこちら
- 『丸山眞男書簡集』全5巻はこちら
- 『丸山眞男話文集』全4巻はこちら
- 『丸山眞男の世界』「みすず」編集部編はこちら
- 萩原延壽『自由の精神』はこちら
- 『鶴見俊輔書評集成』 1 はこちら
- 『鶴見俊輔書評集成』 2 はこちら
- 『鶴見俊輔書評集成』 3 はこちら
- 松尾尊兊『民本主義と帝国主義』はこちら
- テツオ・ナジタ『Doing 思想史』平野克弥編訳はこちら
- 笹倉秀夫『丸山眞男の思想世界』はこちら
- 飯田泰三『戦後精神の光芒』はこちら
- ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』[増補版]大島かおり訳《始まりの本》はこちら
- 原武史『可視化された帝国』[増補版]《始まりの本》はこちら
『アウグスティヌスの愛の概念』

ハンナ・アーレント 千葉眞訳
- ハンナ・アーレント『過去と未来の間』引田隆也・齋藤純一訳はこちら
- ハンナ・アーレント『暴力について』山田正行訳はこちら
- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』 1 大久保和郎訳はこちら
- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』 2 大島通義・大島かおり訳はこちら
- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』 3 大久保和郎・大島かおり訳はこちら
- ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン』大久保和郎訳はこちら
- ハンナ・アーレント『ラーエル・ファルンハーゲン』大島かおり訳はこちら
- 『アーレント政治思想集成』 1 齋藤純一他訳はこちら
- ルッツ編『アーレント=ハイデガー往復書簡』大島かおり・木田元訳はこちら
- 『アーレント=ヤスパース往復書簡』 1 大島かおり訳はこちら
- 『アーレント=ヤスパース往復書簡』 2 大島かおり訳はこちら
- 『アーレント=ヤスパース往復書簡』 3 大島かおり訳はこちら
- エティンガー『アーレントとハイデガー』大島かおり訳はこちら
- ヤング=ブルーエル『なぜアーレントが重要なのか』矢野久美子訳はこちら
- 矢野久美子『ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考の場所』はこちら
- 『ロールズ 哲学史講義』上 坂部恵監訳はこちら
- 『ロールズ 哲学史講義』下 坂部恵監訳はこちら
- A・マッキンタイア『美徳なき時代』篠崎榮訳はこちら
- ベラー他『善い社会』中村圭志訳はこちら
- S・S・ウォリン『政治学批判』千葉眞他編訳はこちら
- S・S・ウォリン『アメリカ憲法の呪縛』千葉眞他訳はこちら
- トニー・ジャット『荒廃する世界のなかで』森本醇訳はこちら
* 第1回配本 (2011年11月・6冊)
『臨床医学の誕生』

ミシェル・フーコー 神谷美恵子訳
[斎藤環解説]
- ビンスワンガー/フーコー『夢と実存』荻野恒一他訳はこちら
- M・ボス編『ハイデッガー ツォリコーン・ゼミナール』木村敏・村本詔司訳はこちら
- V・ヴァイツゼッカー『ゲシュタルトクライス』木村敏・濱中淑彦訳はこちら
- V・ヴァイツゼカー『パトゾフィー』木村敏訳はこちら
- M・メルロー=ポンティ『知覚の現象学』 1 竹内芳郎・小木貞孝訳はこちら
- M・メルロー=ポンティ『知覚の現象学』 2 竹内・木田・宮本訳はこちら
- M・メルロ=ポンティ『意識と言語の獲得』木田元・鯨岡峻訳はこちら
- 中井久夫『西欧精神医学背景史』《みすずライブラリー》はこちら
- ピエール・ジャネ『症例 マドレーヌ』松本雅彦訳はこちら
- ミシェル・ド・セルトー『ルーダンの憑依』矢橋透訳はこちら
- 『神谷美恵子コレクション』全5冊はこちら
『二つの文化と科学革命』

チャールズ・P・スノー 松井巻之助訳
[S・コリーニ解説(増田珠子訳)]
- J・R・ブラウン『なぜ科学を語ってすれ違うのか』青木薫訳はこちら
- T・フランセーン『ゲーデルの定理――利用と誤用の不完全ガイド』田中一之訳はこちら
- T・S・クーン『科学革命の構造』中山茂訳はこちら
- T・S・クーン『科学革命における本質的構造』安孫子誠也・佐野正博訳はこちら
- T・S・クーン『構造以来の道』佐々木力訳はこちら
- C・C・ギリスピー『客観性の刃』島尾永康訳はこちら
- C・C・ギリスピー『科学というプロフェッションの出現』島尾永康訳はこちら
- U・セーゲルストローレ『社会生物学論争史』 1 垂水雄二訳はこちら
- U・セーゲルストローレ『社会生物学論争史』 2 垂水雄二訳はこちら
- 中村禎里『日本のルィセンコ論争』《みすずライブラリー》はこちら
『天皇の逝く国で』
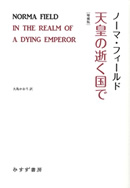
[増補版] ノーマ・フィールド 大島かおり訳
- ノーマ・フィールド『祖母のくに』大島かおり訳はこちら
- ノーマ・フィールド『へんな子じゃないもん』大島かおり訳はこちら
- ノーマ・フィールド『源氏物語、〈あこがれ〉の輝き』斎藤和明他訳はこちら
- テッサ・モーリス=鈴木『辺境から眺める』大川正彦訳はこちら
- 『謝花昇集』伊佐眞一編はこちら
- 明田川融『沖縄基地問題の歴史――非武の島、戦の島』はこちら
- 新城郁夫『沖縄を聞く』はこちら
- 羅英均『日帝時代、わが家は』小川昌代訳はこちら
- 戸谷由麻『東京裁判――第二次大戦後の法と正義の追求』はこちら
- A・ゴードン『日本の200年――徳川時代から現代まで』上 森谷文昭訳はこちら
- A・ゴードン『日本の200年――徳川時代から現代まで』下 森谷文昭訳はこちら
- A・ゴードン編『歴史としての戦後日本』上 中村政則監訳はこちら
- A・ゴードン編『歴史としての戦後日本』下 中村政則監訳はこちら
- 『東アジア人文書100』[発行・東アジア出版人会議/発売・みすず書房]はこちら
『可視化された帝国』

近代日本の行幸啓
[増補版] 原武史
- 丸山真男『戦中と戦後の間』はこちら
- 藤田省三『異端論断章』はこちら
- 萩原延壽『自由の精神』はこちら
- ジョン・W・ダワー『昭和』明田川融監訳はこちら
- H・ハルトゥーニアン『歴史と記憶の抗争』K・M・エンドウ編・監訳はこちら
- テツオ・ナジタ『Doing 思想史』平野克弥編訳はこちら
- R・ジェラテリー『ヒトラーを支持したドイツ国民』根岸隆夫訳はこちら
- J-M・アポストリデス『機械としての王』水林章訳《みすずライブラリー》はこちら
- 北一輝著作集 1 『国体論及び純正社会主義』神島二郎解説はこちら
- 永山正昭『星星の火』平岡茂樹・飯田朋子編はこちら
- 『現代史資料』全45巻・別巻1[オンデマンド版]はこちら
- 『続・現代史資料』全12巻[オンデマンド版]はこちら
『哲学のアクチュアリティ』

初期論集
[初書籍化] テオドール・W・アドルノ 細見和之訳
- 『アドルノ 文学ノート』 1 三光長治他訳はこちら
- 『アドルノ 文学ノート』 2 三光長治他訳はこちら
- Th・W・アドルノ『キルケゴール』山本泰生訳はこちら
- 細見和之『アドルノの場所』はこちら
- E・W・サイード『故国喪失についての省察』 2 大橋洋一他訳はこちら
- E・W・サイード『音楽のエラボレーション』大橋洋一訳はこちら
- マーティン・ジェイ『弁証法的想像力』荒川幾男訳はこちら
- S・ヒューズ『大変貌――社会思想の大移動1930-1965』荒川・生松訳はこちら
- R・G・コリングウッド『自然の観念』平林康之他訳はこちら
- シリーズ《エコロジーの思想》はこちら
『進歩の終焉』
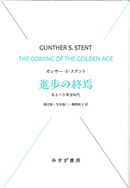
来るべき黄金時代
ガンサー・S・ステント 渡辺格・生松敬三・柳澤桂子訳
[木田元解説]
- ジョン・グレイ『わらの犬――地球に君臨する人間』池央耿訳はこちら
- トニー・ジャット『荒廃する世界のなかで――これからの「社会民主主義」を語ろう』森本醇訳はこちら
- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 1 柿沼敏江訳はこちら
- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 2 柿沼敏江訳はこちら
- 中沢新一『芸術人類学』はこちら
- D・M・ベルーベ『ナノ・ハイプ狂騒』上 五島綾子監訳・熊井ひろ美訳はこちら
- D・M・ベルーベ『ナノ・ハイプ狂騒』下 五島綾子監訳・熊井ひろ美訳はこちら
- ヴァンダーミーア/ペルフェクト『生物多様性〈喪失〉の真実』新島義昭訳はこちら
- H・E・デイリー『持続可能な発展の経済学』新田・藏本・大森訳はこちら
- N・ジョージェスク=レーゲン『エントロピー法則と経済過程』高橋・神里他訳はこちら
- 玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』はこちら
- 上村芳郎『クローン人間の倫理』はこちら
- G・R・テイラー『人間に未来はあるか』渡辺格・大川節夫訳はこちら
- G・R・テイラー『地球に未来はあるか』大川節夫訳はこちら
* 続刊予定

『行動の構造』上・下
M・メルロ=ポンティ 滝浦静雄・木田元訳
『沈黙の世界』
マックス・ピカート 佐野利勝訳
『知性改善論・短論文』
バールーフ・デ・スピノザ 佐藤一郎訳
『アメリカ論』(仮)
W・C・ウィリアムズ
[以下続刊]
